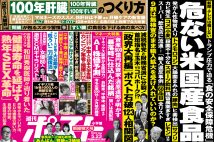相模鉄道のキャラクター「そうにゃん」(時事通信フォト)
「1950年まで、横浜駅の西口は広大な空き地になっていました。そこを相鉄が買い取り、老舗百貨店の高島屋を誘致したのです。そこから横浜駅西口は発展を遂げています。特に西口は相鉄が発展させたと言っても過言ではありません。そうした歴史がありますので、東急直通線の開業後も横浜駅が相鉄の中心軸であることは変わりません。これからも横浜駅を引き続き利用してもらえるように、『YOKOHAMA どっちも定期』を始めることにしたのです」(同)
先述したように、神奈川県内のみを走っていた相鉄にとって東京進出は悲願で、2019年にようやくJR直通線で東京とつながった。今回の東急直通線の開業は、2019年ほどのインパクトはない。それでも東急直通線は、東京につながるという意味以上に新横浜駅にアクセスできるようになったという点が大きい。
悲願の東京進出から知名度向上へ
新横浜駅は、1964年に東海道新幹線が運行を開始するとともに開業した。当時は駅周辺に農地が広がり、おしゃれで都会的というイメージがある横浜市の玄関口にしては、のどかだった。それから半世紀以上が経過した現在、地元民から駅裏と認識されている篠原口側は住宅地然としているものの、北口は駅ビルが立ち、日産スタジアムや横浜アリーナなどの大規模集客施設が並ぶ。
利用者数も以前とは比べものにならないほど増え、2008年からは東海道新幹線の全列車が停車するようになる。
他方で、新横浜駅までのアクセスは決していいとは言えなかった。新横浜駅は横浜駅や桜木町駅といった横浜市の中心部から離れているので、新幹線を使用する機会がなければ足を運ぶことはない。
相鉄の新横浜線開業は、新横浜駅へのアクセスが飛躍的に向上する。それと同時に、街の発展が著しく利用者が増加傾向にある新横浜駅とつながることになる。新横浜駅とつながることで、相鉄の利用者増が見込める。それだけではなく、相鉄沿線の活性化も期待できる。
「相鉄は神奈川県を地盤とする鉄道会社で、大手私鉄になってから30年以上が経過しています。それにも関わらず、全国的な知名度が低いことは社内でも問題意識として共有されていました。そのため、沿線外の人たちに対して知名度を向上させることが課題になっていたのです。新横浜は東海道新幹線の全列車が停車する駅ですから、名古屋や大阪などから足を運ぶ観光客やビジネスマンが多く乗降します。相鉄が新横浜駅に乗り入れることになれば、相鉄の知名度は東京圏のみならず全国的に向上すると考えています」(同)
相鉄は知名度を向上させるための取り組みとして、自社のブランドイメージを刷新するプロジェクト「デザインブランドアッププロジェクト」を2013年にスタートさせている。同プロジェクトは、2019年のJR直通線の開業を見越して相鉄を広くPRする目的が含まれていた。なぜなら、相鉄の電車が東京都心部へと乗り入れることで、自社線外でも相鉄の電車を目にする機会が増えるからだ。