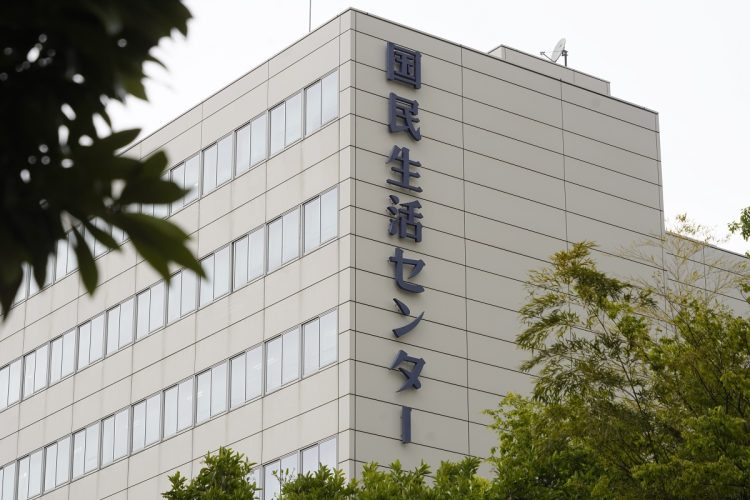国民生活センターは土日祝日も相談できる(時事通信フォト)
賃貸不動産も投資のひとつ、利益を出さなければ大家であろうと管理会社であろうと損を被るのは自分自身である。しかし「言ってみるか」でそのリスクの一部を借主に負担させることもできる。事例の通り、たとえ入居していなくとも。事例1は極端とはいえ、事例2のような場合はどうすればいいのか。
「経年劣化だけなら国交省のガイドライン(前述)を提示する、あるいは『消費者センターに通報します』と毅然と言えば(敷金が)返って来る場合も多いと思います。裁判するぞ、でもいい。そんなので効くのかと言われるかもしれませんが案外効くものです。絶対じゃありませんけど。本音のところ、大半の貸主も面倒くさいことはやりたくありませんし、面倒くさい相手は嫌がります。高級賃貸ならともかく、家賃数万円のワンルームとか1Kのアパートとかでしょう、それはそれで割に合いませんから。とにかく「言ってみるか」なんですよ。この業界によくある話です。まあ、駆け引きですね。昔ほどの無茶はできませんし」
それでも冒頭の男性に限らず、賃貸住民の多くから聞かれる「原状回復」で揉めた、「敷金」が返ってこないという、今回の国民生活センターの呼びかけそのままの実態がある。
「借主にも善管注意義務(民法第400条「善良なる管理者の注意義務」)を怠る人もいるわけで、それが理由で敷金を引かせてもらう場合もあります。でもあからさまに酷い使い方でもない限り、畳の表替えどころか新調とか、壁紙の全面張替えなんてまあ、国交省のガイドライン的にも認められないでしょうね。でも「言ってみるか」なんですよ」
異業種や独立起業した新規参入の賃貸業者による無茶な請求
ヒアリングによれば「納得できない原状回復」として畳や壁紙の他、ガス器具の交換、フローリングの総張替え、水回りの交換、照明器具の交換など「それは自分の資産および次の客のためのリフォームでは」というものがあった。どれも借主がありえない使い方で台無しにしたとか、破壊したとかでない限りはガイドライン的に経年劣化だろう。「10年住んだら110万円請求された」という話もある(この件は交渉の末、敷金分のみで決着)。