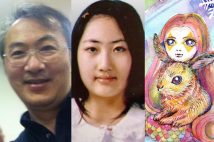坂口氏の婦人部長時代に開かれた幹部会の様子を報じた聖教新聞(1988年4月28日付)。写真左に池田氏が写っている
──平和の党の色が見えないんですが。
「見えないところで努力をしているんですよ。メディアは公明党を報じないから。どういう動き? 知りません」
何人かに声をかけたが「平和の党はかくあれ」といった声はなく、熱が感じられない。
「学会婦人部」は、いつの間にか主体的意思を持たない「空」の組織に変質してはいないか──。そんな疑問が浮かんだのは2016年6月、当時の舛添要一・都知事を支えていた都議会公明党が突如批判に転じ、辞任に追い込んだ時だ。
公明都議らは「婦人部の突き上げがある」と言った。都議会で野党から小池(百合子)与党に転じた時も、「婦人部が小池支持で固まった」という情報が流れた。いずれも婦人部の怒りは可視化されず、もしや公明党は急ハンドルの政治判断のエクスキューズとして「婦人部が怒っている」という言説を使っているのではないか。そんな嫌な感じが記憶にこびりついていた。
「家の平和も作れないのに」
そもそも、なぜ「婦人部」はそんなにも強い存在感を示してきたのか。
学会に既婚女性らの「婦人部」ができたのは1951年。公明党の前身の公明政治連盟が結成される10年前だ。婦人部の下支えを得て党は選挙で議席を急伸させてきた。
100万人、200万人ととてつもないスピードで会員数が増加したのは、戦後、経済発展する大都市で劣悪な生活環境におかれていた都市生活者たちが入会したからだ。
生活や仕事に不安を抱える人々に、平和や環境問題の理想と現世利益追求がまざった新宗教が受け入れられた。
団塊の世代より少し後輩にあたる元理事長・正木正明氏を父に持つ、元学会本部職員でライターの正木伸城氏(41)が幼少期をこう語った。
「我が家ではある時期から私や弟が留守番をすることが多くなりました。父は仕事で出張に飛び回っているし、母は婦人部の会合で家を不在にしがち。寂しくて母に泣きついたこともあるし、高校生の頃、父に『家の平和も作れないのに何が世界平和だよ』と怒りをぶつけたこともある」