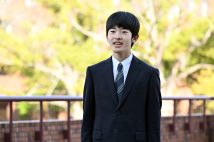会見に出るジャヌス監督(右から2番目)とリリー・フランキー(右から3番目)
「記事を読んで最初に感じたのは、孤独死してしまう人たちがなぜ、そんなにも長期間、誰にも発見されなかったのか、という疑問です。なぜそんなことが起こり得るのか。それは『あなたは価値がない』『他人にとってどうでもいい存在である』という事実を示しているようで、フィリピン人の私にとってはすぐには理解できませんでした」(ジャヌス、以下同)
心を揺さぶられたジャヌスは、孤独死をテーマにした映画制作に乗り出した。孤独死の実態やその背景にある日本社会の問題を理解するため、腐乱死体のあった部屋を清掃する特殊清掃人や日本人ジャーナリスト、フィリピンを専門にする日本の大学教授、企業の出世コースから外れた窓際族などに通訳を交えて聞き取り調査を重ね、構想を練り上げていく。その過程でジャヌスは、自問を繰り返した。
「人生において自分の存在が誰かに影響を及ぼす時、私たちはそこに人生の意義や価値を感じるのだと思う。1人で死ぬことは物理的には可能だと思うし、普通は誰かがその人のことを思い出してくれるでしょう。でも孤独死というのは、誰からも思い出されない、つまりは誰にもその存在が影響を及ぼさない、ということなのでしょうか。そんな問いが、映画作りの動機にもなりました」
ジャヌスは当時、フィリピンの首都マニラの自宅で祖母の面倒をみていたため、親族の死を身近に感じる環境にいた。死という最期は、それまでの人生で積み重ねてきた結果である、と言われがちだ。言い換えれば、どのような最期を迎えるかでその人の価値が決まる。だが、ジャヌスはその考え方には否定的だった。
「人生は成功と失敗の繰り返しの上に成り立っている。ですが、孤独死はまるで『人生の敗者』であるかのように捉えられてしまう。ライフサイクルの問題ではないでしょうか。亡くなったときは、人生が不調で、その時に死を迎えただけではないかと。私はそう信じたいです」