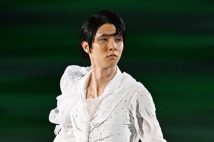ヒグマ対策を担っていた元レンジャーが語る知床の現実(イメージ、時事通信フォト)
北海道の福島町と羅臼岳で相次いだヒグマの襲撃による死亡事故。凄惨な被害に恐怖心を抱く人が多い中、現地でレンジャーとして日々、ヒグマと向き合う対策プロたちは何を思うのか。ノンフィクションライターの中村計氏が取材した。(文中敬称略)【前後編の前編】
* * *
「これまで知床でクマとの大きな事故が起きなかったことの方が奇跡だったんです」
知床でかつてヒグマ対策を担っていた元レンジャーは、過熱気味のヒグマ事故の報道に釘を刺すように言う。
先月14日、羅臼岳の登山者がヒグマに襲われ、亡くなった。北海道が記録を公表している1962年以降、知床において観光客がヒグマとの接触事故で死亡したのは初めてのことだ。
以降、ネット記事では連日のように「殺人グマ」「人食いグマ」等のいたずらに恐怖心をあおる言葉が並んでいる。
元レンジャーの言葉は冷静だった。
「今回の事故に接し、ヒグマ管理に従事していた人たちの中で、あり得ないことが起きたと言う人はいないと思います。リスクがゼロだと思っていた人はいませんから」
毎日新聞の9月1日の配信記事には、こんなセンセーショナルな見出しが躍った。
〈「知床は終わる」ヒグマとの「共生神話」崩壊で揺れる観光地〉
元レンジャーはこのタイトルに対して「訴えたくなります」と冗談めかしつつ、続けた。
「神話でも何でもない。人の汗で安全が保たれていただけなんです。しかも、ギリギリのところで。だって、こんなにたくさんヒグマがいるところに、これだけいろんな人が入ってくるわけですよ」
アイヌ語で「大地の突端」という意味を持つ約70kmの知床半島は、世界でも稀に見るヒグマの高密度地域だ。かつ、知床は2005年に世界自然遺産に登録されてからというもの、年間、約180万人もの観光客が押し寄せる一大観光地になった。人とヒグマの距離の近さということでは国内随一と言っていい。
ヒグマが道路に現れると、それを見物するための「クマ渋滞」が起きる。禁止行為の餌付けを行う客もいた。高確率でヒグマが現れるポイントにはカメラマンが群がり、中には近距離から撮影を試みる無法者もいる。知床を訪れるたび、これでよくぞ大事故が起きないものだと思ったものだ。
元レンジャーは語る。
「われわれは相当、いろいろなことをやってきた。トレッキングコース内に高架木道をつくり、山にフードロッカー(注:ヒグマが開けられない仕組みの食糧保管庫)を担ぎ上げた。お願いベースですけど、夕方、テントを回りチラシを配って注意喚起をしたり。クマが遊歩道などに現れたら、ゴム弾や花火で追い払ったり。相応の労力とコストがかかっているわけです。その積み重ねで、何とか事故を防いできた」