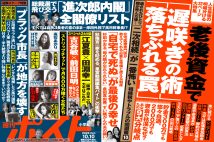親と子供の性格が似る確率は
「子は親の性格を受け継ぐ」という主張の真偽も確かめてみよう。親の性格は、本当に子供に似るのだろうか。
たしかに、性格には遺伝が大きく影響する。「勤勉さ」「社交性」「好奇心」「不安症」などの性格は、いずれも遺伝率が約50%だとされ、この数値はどの文化圏でも変わらない。
しかし、遺伝率とは“集団内の違いの原因がどこにあるか”を示す指標であって、親子の類似度は何もわからない。そのため、遺伝率が高いからといって、必ずしも「カエルの子はカエルになる」とも言えない。
この問題には長い研究の歴史があり、1930年代から多くの調査が行われている。なかでも精度が高いのはエディンバラ大学などの研究で、1000組以上の家族の性格データを集めて分析を行ったところ、親と子供の性格が似る確率はだいたい39%だった。
これに対して、その子供がまったくの他人と似た性格になる確率は33%だったというから、そこまでの違いはない。 親子の性格は他人よりわずかに似るものの、統計的には『ほとんど他人』と言ってもいいぐらい異なることになる。「勤勉な親の子供は勤勉になりやすい」などとは、とても言えない数値だ。こういった結果が出るのは、私たちの性格が複数の遺伝子の組み合わせで決まるからだ。
性格は一生変わらないのか
特定の性格が生まれる背景には、数千の遺伝子が関わると考えられており、それらひとつひとつが組み合わさって複雑な“モザイク”を作り上げている。
それはあたかも数千のレゴブロックを組み合わせて遊ぶようなものであり、そこから生まれる作品のバリエーションは無数に存在する。「外向性を決める遺伝子」や「不安になりやすさを決める遺伝子」のように、単純な要因が存在するわけではない。
さらに言えば、人間の性格は、私たちが人生のなかで味わった体験によっても変化する。その代表例は“離婚”で、ある研究によれば、パートナーと別れた参加者の性格の変化を調べたところ、その直後から好奇心が低下し、人見知りな性格に変化する者が多かった。また、別の研究では、会社で昇進した人は勤勉な性格になりやすく、病気や死別を味わった人は神経症的になりやすい傾向も見られたという[7]。こういった現象が起きる理由はまだ明らかではないが、おそらくライフイベントの変化により、コミュニケーションの質が変わったのが原因なのだろう。
遺伝の複雑さに加えて人生の体験まで影響するのだから、親子といえど性格に違いが出るのは当たり前だ。すべてをひっくるめて考えれば、私たちの性格は柔軟なオープンシステムだと言えるだろう。
(了。第1回を読む)
【著者プロフィール】
鈴木 祐(すずき・ゆう)
1976年生まれ、慶応義塾大学SFC卒。16才のころから年に5000本の科学論文を読み続けている、人呼んで「日本一の文献オタク」。大学卒業後、出版社勤務を経て独立。雑誌などに執筆するかたわら、海外の学者や専門医などを中心に約600人にインタビューを重ね、現在は月に1冊のペースでブックライティングを手がける。現在まで手がけた書籍は100冊超。科学論文で得た知識を仕事の効率アップに活かし、1日に2~4万文字の原稿を量産するいっぽうで、ライター界では珍しい「100%締め切りを守る男」としても知られる。近年では、自身のブログ「パレオな男(http://yuchrszk.blogspot.jp/)」で健康、心理、科学に関する最新の知見を紹介し続け、現在は月間250万PV。近年は自著「最高の体調」(クロスメディアパブリッシング)や「パレオダイエットの教科書」(扶桑社)などを上梓し、ヘルスケア企業などを中心に、科学的なエビデンスの見分け方などを伝える講演なども行っている。