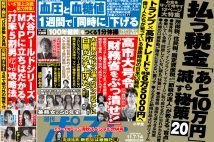そうした本質の捉え方は数学の研究にも通じると。
「どんな多角形の外角の和も三百六十度のように、千差万別、無数にある多角形の中から本質を捉え、定理として表現する数学と、文学、特に詩はかなり似ていて、自分の思いや本当に言いたいことを、時にこれ以上はないほど簡潔に美しい形で代弁してくれたりする。
その対象が数や図形なら数学、人間なら文学になるんだけど、本質を抽出する行為自体は誰でも日常的にやっていることなんですよ。だから寅さんの言動と数学的発想の共通点を見出して山田監督に驚かれたりするわけで、自称・数学嫌いな方も単なる食わず嫌いか、または怠け者か、そのどちらかだと思います」
本書の魅力は、著者が出会い、影響を受けた人々の魅力そのものでもある。
高校の頃、〈どんな地図も、4色の色を使って、隣接する国どうしが同じ色にならないように塗り分けることができる〉ことを証明する通称「4色問題」(1976年まで未解決)と出会い、そこからグラフ理論、さらには離散数学へと研究を進めた秋山氏にとって、ミシガン大学のフランク・ハラリー教授は最初にして最大の師。同時に〈♪ボスしけてるぜ〉(by忌野清志郎)と文句の一つも言いたくなるほど、「ケチで恩着せがましい」恩師とのエピソードを硬軟交えて書いた上で、〈人は、自分が愛情を抱ける対象からしか、学ばない〉というゲーテの言葉を引くのである。
「とにかく口うるさいし、マクドナルドやサーカスのタダ券はくれるけど、金のかかるものは一切くれない。ジュースを買ったら買ったで氷を抜いて、その体積分の料金を返せと店の人に絡んだり、大のビュッフェ好きで、一皿定額の時は山盛りにした料理をこぼさないようにそーっと私と歩く姿を笑われたり、超個性的なやつではありました(笑)。
この歳になってようやくです。彼は人目を気にしないだけで、愛情もちゃんとある人だったと今はわかる。だから、いいこともあるんですよね、長生きすると」