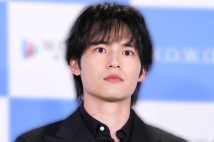AIが予測「クマ遭遇地形が丸わかり」【秋田】
開発したのは上智大学大学院の深澤佑介・准教授(応用データサイエンス学位プログラム)。かつて在籍したNTTドコモでは「人口統計データ」分析を手掛けていた。
「エリアごとに人の流れに基づき、移動や店の需要の変化を予測する研究などをしていました。上智大学に移籍した2023年頃、秋田県でクマとの遭遇が激増したのを知り、『クマといつどこで遭遇するのか』についての研究を始めたのです」(深澤氏)
実際、クマの分布域はじわじわ広がっているという。クマ研究の第一人者である小池伸介・東京農工大教授が言う。
「クマの分布域はこの40年間で約2倍になっています。一昔前は、クマは奥山に、人間は平地に住み、その間の中山間地域で耕作や林業が行なわれていました。しかし、少子高齢化や都市への一極集中が進むなかで中山間地域に人がいなくなり、耕作地が放棄されて森に回帰していった。そういった場所がクマの新たな生息地になったのです」
人とクマが隣り合って暮らす状況が生まれてきたなかで、今年や2023年のようなドングリの不作が起きると、クマは通常とは違う行動(市街地への出没)を繰り返すという。
そうした危機的状況に対処するため、AI予測マップでは、過去の遭遇記録に気象・標高・ブナの実の豊凶情報などの自然要因と、人口分布・道路の有無・土地の利用状況といった社会的・環境的要因をAIに学習させている。
「例えば自治体の発表するクマ遭遇の位置情報に、『土地被覆図』を重ねると、落葉樹が多い、湿地であるなど遭遇した場所の土地利用状況がわかります。それ以外にも道路の有無や人口密度、高齢化率などを組み合わせて、“人とクマが交わる場所”を導き出しています」(深澤氏)
AI予測は人の居住エリアを対象にし、1キロ四方ごとに遭遇リスク(クマとの遭遇確率)を5段階で評価している。日常的に人の気配がない山奥などは対象外だ。