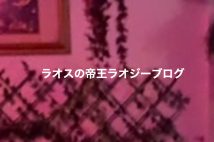ラオスを訪問された愛子さまと異例の発言をした高市首相(写真右/Getty Images、左・撮影/横田紋子)
11月17日、愛子さまはラオスへの公式訪問のため、同国の首都ビエンチャンに降り立たれた。ラベンダー色の民族衣装「シン」に身を包んだプリンセスは、周囲のスタッフを招き寄せると、晴れやかな笑顔で写真に収まった。
ベトナム戦争での激しい戦闘、そして長引く貧困という厳しい道のりを歩んできたラオス。現在、その貧困に乗じた一部の日本人による蛮行が、大きな問題になっている。
「アジア最貧国ともいわれるラオスの農村家庭では、子供たちが売春のために売られていくことも日常茶飯事だといいます。これに目をつけた日本人男性が、幼い子供たちを“買う”ために、こぞって渡航しているという実態があるのです。
事態を重く見た駐ラオス日本国大使館は今年6月、ラオスで児童買春を行わないように、と異例の注意喚起を発しました。今年8月には、ラオスで児童買春に及んだ日本人男性2人が『児童ポルノ禁止法違反』で逮捕されています」(国際ジャーナリスト)
愛子さまのラオスご訪問が発表されたのは今年5月末。大使館による異例の注意喚起は、それから1か月足らずでの発表だった。
「買春に対する注意喚起は愛子さま来訪のための露払いだとみる向きもあります。実際、愛子さまのご訪問で同国の“闇”の部分に光が当たり、児童買春を行う日本人の足も遠のくのではと期待する声も上がっている。愛子さまもこうした現状はもちろんご存じで、解決を強く願われています」(宮内庁関係者)
愛子さまの現地へのご出発を間近に控えた11月11日の東京・永田町では、国会答弁で高市早苗首相(64才)が、愛子さまに共鳴するかのような発言をしていた。
「売春防止法について、“買春行為の罰則化を検討するように”と、法務大臣に指示を出したのです。これまで、時の首相が買春行為の罰則化について言及したことはほとんどなく、異例の発言といえる。法改正に向けた、高市首相の強い決意が感じられました」(政治部記者)
売春防止法は、1957年の施行当初から大きな矛盾をはらんでいるという。「岡野法律事務所」弁護士の伊倉秀知氏が解説する。
「同法では“売る側”に罰則が定められている一方で“買う側”に罰則はありません。売春行為そのものには罰則規定はないものの、『客待ち』『売春のあっせん』『勧誘』『場所の提供』など、売買春を助長・あっせんする行為は逮捕や罰則の対象となる。つまり“売春する側”のみが処罰され得る構造となっているのです」
一方、世界に視野を広げると、“買う側”に罰則を科すのが、先進国のスタンダードだ。アメリカでは売る側、買う側双方に、さらにイギリスやフランスでは、“買う側にこそ問題がある”という考え方で、買春する側にのみ、罰則が設けられている。日本の売春防止法が構造的に抱える矛盾は、かねて国際社会から厳しい目を向けられてきた経緯があり、高市首相の発言は、国際社会に足並みをそろえる大きな一歩となった。
「愛子さまのご訪問のタイミングも重なり、ラオスでの児童買春は国際的にも議論の的となった。高市首相も当然、この問題は把握しているはずで、買春側の罰則化に踏み込んだ背景には、ラオスの悲惨な実態を知った愛子さまに共感した部分もあったのかもしれません。愛子さまも、高市首相の発言に納得されていることでしょう」(皇室ジャーナリスト)
※女性セブン2025年12月4日号