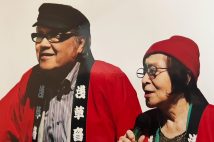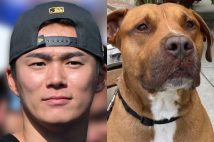北海道に生息するヒグマ(写真/Getty Images)
今後も出てくる「新しい恐怖」に私たちはどう立ち向かえばいいのか
そのほか「より用心深くという細かいノウハウはどんどん増え続け、お役所も個人も自粛ムードがどんどんエスカレートする」という共通点もあります。「こんな対策もある、あんな方法もある」と言っているほうが賢そうに見えるし、「もし何かあったら」「もし批判されたら」という印籠の前では誰もがひれ伏さざるを得ません。
今後予想されるのが「喉元を過ぎると熱さを忘れて、あいかわらず危険性は十分にあるのに、世の中の関心が離れて話題にならなくなる」という共通点。どんな問題にせよ、喉元を過ぎると見事に忘れられてしまうとなると、話題になっているときに抱いている恐怖心や警戒心は、もしかしたら抱く必要がないということでしょうか。
忘れっぽいのが人間のサガとわかってはいても、クマなりコロナなりといった「怖いもの」に注目が集まると、ひとしきり騒がずにはいられません。ただ、少なくともクマ騒動に関しては、安全な地域でテレビやスマホの画面を見ながら「うわー、怖い」と言っているのは、しょせん娯楽として消費しているに過ぎないことは自覚しておきたいものです。
「クマ騒動」と「コロナ騒動」の両方を経験した私たちとしては、今後も次々に出てくるであろう「新しい恐怖」に対して、どう立ち向かえばいいのか。
今こそ噛みしめたいのが、コロナ禍の頃によく言われた「正しく怖がる」というフレーズ。やみくもに騒ぐほうが、目先の充実感や達成感は得られますが、あとで振り返ると「なんであんなに騒いでいたんだろう」と思ってしまいます。
ちょっと恥ずかしくなるだけならまだしも、誰もがひとつ間違えると、他県ナンバーのクルマに石を投げつける的な「人としてどうかしている行為」をしでかすかもしれません。己の「正義感」や、その時々の「正しい意見」がいかにアテにならないかも、ふたつの騒動の共通点を通じて十分に学ぶことができます。
私たちは恐怖心や怒りや敵愾心を煽られると、我を忘れてヘンな考えや行動に走ってしまいがち。猛獣やウイルスだけでなく、ニュースを見聞きして激しく感情が揺さぶられたときは、くれぐれも気をつけたいですね。たとえば……いや、話が長くなりそうなので、各自でイメージをふくらませてもらうことにして、このへんで失礼いたします。