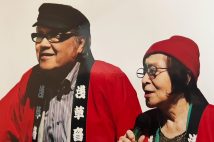さて、作詞家・星野哲郎をご存じだろうか? まさに、現在「鼻タレ小僧」以上の世代なら知らない人はいないぐらいの著名人で、たとえ個人名を知らなくても彼が作詞した曲に触れたことの無い人はいないのではないか。あらためてインターネット上の百科事典ウィキペディアでその経歴を見てみよう。長文にわたるので、一部抜粋して紹介する
〈星野哲郎(ほしのてつろう、本名:有近 哲郎(ありちか てつろう)、1925年9月30日-2010年11月15日)は、日本の作詞家であり、戦後歌謡界を代表する作詞家の一人。各所で「星野哲朗」という表記がされることがあるが、「哲郎」が正しい表記。「有田めぐむ」「阿里あさみ」など、数多くのペンネームが存在する。
山口県大島郡森野村(後に東和町→現・周防大島町)出身で、東京都小金井市に在住していた。(中略)山口県大島郡森野村(現・周防大島町)和佐に生まれる。森野村立開導小学校、山口県立安下庄中学校(現・山口県立周防大島高等学校安下庄校舎)を経て、1946年(昭和21年)、官立清水高等商船学校(現・東京海洋大学)を途中結核で休学しながらも卒業。翌年、日魯漁業(後のニチロ、現・マルハニチロ)に入社、遠洋漁業の乗組員となる。しかし就職して数年後、腎臓結核のために船を下りざるを得なくなり、腎臓を摘出。郷里周防大島にて4年にわたる闘病生活を余儀なくされる。〉
彼の代表作はとても全部紹介できないが、渥美清『男はつらいよ』、北島三郎『兄弟仁義』『函館の女』、小林旭『自動車ショー歌』『昔の名前で出ています』、水前寺清子『涙を抱いた渡り鳥』『いっぽんどっこの唄』『三百六十五歩のマーチ』、鳥羽一郎『兄弟船』、都はるみ『アンコ椿は恋の花』等々がある。まさに「戦後歌謡界を代表する作詞家の一人」であり、もしも星野がいなかったら戦後歌謡史は大きく変わっていたことがわかるだろう。代表作のなかの『兄弟船』は漁船員としての経験を生かしたもので、いまでも彼らの愛唱歌となっている。
遅れた「ストマイ」の普及
ここで注目していただきたいのは、その漁船員としての経歴で、じつは星野が結核になるまで乗っていたのが、韓国海軍に「撃沈」させられた『第六あけぼの丸』だったことだ。つまり、もし結核にならなければ彼自身、北の海で生涯を終えていた可能性が高いのである。ネット上の情報では「星野が乗っていた船と沈没した船は、同じ『あけぼの丸』でも船体が違う」という見解もあるが、これは別に問題にならない。
問題にならないというのは、新造船に船名が引き継がれた場合は、「先代」の船の乗組員すなわちクルーが引き続き新造船に乗り込むことが普通だからだ。それは、たとえばアメリカのSFドラマシリーズ『スタートレック』などを見てもわかることで、いわば船乗りの常識である。つまり星野は、結核にならなければ一九五五年にこの世を去っていた可能性が非常に高いのである。