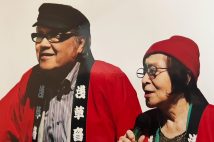作家の井沢元彦氏による『逆説の日本史』
ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その7」をお届けする(第1472回)。
* * *
前回までの数回で、一九五五年(昭和30)における大韓民国初代大統領・李承晩の行動について述べた。それは、一九一九年(大正8)に日本併合下の朝鮮半島で起こった「三・一独立運動」の評価について、それを扇動した「在外朝鮮人(当時)」の代表でもあった李承晩の性格分析が必要だったからであって、決して「余談」をしたわけでは無い。
しかし、今回はあえて余談をしたい。なぜなら、歴史というものの奥深さを知るためには、それが必要だからだ。この稿を書いているちょうどいま、第一〇四代内閣総理大臣に高市早苗・前経済安全保障相が選出された。日本憲政史上初の女性総理大臣の誕生である。つまり二〇二五年(令和7)十月二十一日は、日本の歴史上「後世に記憶される日」になったわけだが、その自民党を中心とした日本の政界には「四十、五十は鼻タレ小僧」という格言(?)があったことをご存じだろうか。
最近はどこの国でも若いリーダーがもてはやされ、高齢の政治家は「老害」などと言われてしまうのでこの言葉も囁かれることは少なくなったが、それでも中高年の人間には納得のいく言葉ではないだろうか。
たしかに、人間は年を重ねるほど人間界の複雑な中身というものがわかってくる。あえて差別語を使えば、「若僧にはわからない世界」である。前にも述べたことがあるが、学問の世界では若い研究者が主導権を握るケースが多い。とくに理系、たとえば数学や物理の分野ではノーベル賞級の功績はしばしば若い研究者によって築かれる。これはやはり若いほうが頭脳の働きも俊敏で、柔軟だからだろう。
ところが、これが唯一あてはまらないのが文科系の歴史や文学に関する部門だ。もちろん若くて柔軟な頭脳は、それまで見落とされていた新しい視点に気がつくことなどで歴史学の発展に貢献はできる。だが、ちょっと考えていただきたい。いかに優秀でも、書斎や研究室にこもってナマの人間とは違う史料だけとつき合い、人づき合いが苦手だなどという若い研究者が本当の歴史の機微というものをつかめるだろうか?
「四十、五十は鼻タレ小僧」なら「人間、六十から一人前」ということになるが、日本の大学や研究機関ではその年齢を過ぎるとすぐに定年になって追い出されてしまう。つまり、それ以降の人生で実感した「人間社会の機微」を、学問の成果に生かすことは難しくなる。結果的に歴史研究とは「ナマの刺身」では無く、「乾燥食品」についての研究になってしまう。
しかし私は幸いにも、専門という形で研究する時代が限定されることも無いし、また定年という形で現役引退を強いられることも無い。歴史学者では無い民間の自由な歴史家だからだ。それゆえ前回述べたように一九一九年の「三・一独立運動」の評価について、一九五五年以降まで踏まえた巨視的な評価ができる。
そして、今回は余談を語ることによって歴史を立体的に見る、歴史学者には不可能な方法で歴史全体を見る方法について語ろう。ただし、これは冒頭にお断りしたとおり本題の一九一九年前後の歴史とはとりあえず関連は無い。だから、本当の余談なのである。