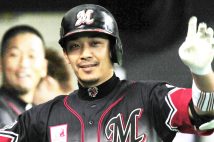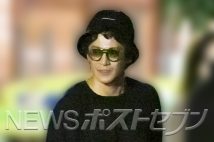消費者の財布のヒモはなかなか緩まない
食料品など生活必需品の値上げが相次ぐ中、いよいよ「脱デフレ」の機運が高まっている。
経団連の榊原定征会長は、加盟する大企業を中心に2年連続となる賃金のベースアップが実現したことや、物価の上昇傾向などを挙げ、「政府・日銀が年内にもデフレ脱却宣言を行う」との見解を示した。
2013年4月より異次元緩和で大量のカネを市場に注ぎ込み、インフレ誘導を行ってきた日銀の自信は揺るぎない。黒田東彦総裁は4月の訪米時に、「日本経済はデフレの制圧に向けた道筋を順調にたどっている」と話し、長く続いたデフレからインフレ局面に転じる現況を“山が動く瞬間”と表現した。
だが、物価の上昇が本格的な個人消費の回復に繋がっているのかは疑わしい。信州大学経済学部の真壁昭夫教授が指摘する。
「肝心の消費者物価(指数)は、今年の3月までは前年対比で3%近い上昇率を示していましたが、そのうち2%は昨年4月の消費増税の引き上げ分。物価の嵩上げ効果もなくなったいまは、0コンマ数%台の水準しか上がっていません。
その理由は、買い控えなど消費者の購買意欲が高まらず、モノを買いたいという人よりもモノを売りたい人のほうが多い需要不足、つまりデフレギャップが起きているからです。これは日本だけでなく世界的に見られる傾向です」
しかも、僅かながらジワジワと上がる物価は、「良いインフレとは言い難い」という。
「食料品などの値段が上がっているのは、円安によって輸入する原材料価格が高騰しているだけ。欲しいモノがたくさんあって、需要が高まったから価格が上がり、生産能力を増強して……と経済の好循環が生まれているわけではないのです。
仮にいまの円安水準が止まってしまえば、それ以上の物価押し上げ要因はなくなってしまうでしょう。ちなみに、1973年に完全変動相場制になって以降、4年以上円安が続いたことはありません。2011年11月に始まった今回の円安も永遠ではないのです」(真壁氏)