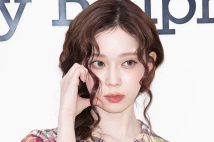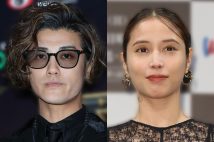電力需給見通しが発表された。すべての原発を停止したままでも夏に高まる電力需要をなんとか乗り切れる見通しではあるが、昨夏より1.6ポイント悪化した4.6%という厳しい状況だ。経営コンサルタントの大前研一氏が、原発の安全性について解説する。
* * *
原発を持つ電力9社が試算した今夏の電力需給見通しが発表された。原発再稼働を織り込まない9社平均の予備率(最大需要に対する供給余力)は4.6%だが、福島第一原発事故前の原発依存度が高かった関西電力と九州電力は、東京電力からの融通(関電38万kW、九電20万kW)によって、ようやく最低限必要とされる3%を確保するという綱渡り状態だ。
融通を受けないと予備率は関電1.8%、九電1.3%にすぎず、しかも3%では、もし大型火力発電所でトラブルが起きたらブラックアウト(大停電)の危険がある。
その一方で、政府は先ごろ閣議決定したエネルギー基本計画で、石炭火力とともに原子力を、昼夜を問わず低いコストで安定的に発電できる「ベースロード電源」と位置付けて再評価した。これに対し、反原発派は「福島の教訓はどうなったのか」と反発している。
だが、政府組織の対応や地元自治体との連携・役割分担、電力会社の情報共有、万一の時の避難対策などのソフト面はともかく、ハード面から見る限り、原発の安全性は福島の教訓に学んで格段に高まっている。
ハード面の福島の教訓とは、2012年7月に上梓した拙著『原発再稼働「最後の条件」』(小学館)などで指摘したように、原子炉自体は自動的にスクラム(緊急停止)できたので「電源さえ喪失しなければ冷却して冷温停止に持っていける」ということだ。すでに東電の柏崎刈羽原発や関電の大飯原発などは、それを踏まえて電源喪失に陥らないための二重三重の対策が講じられている。