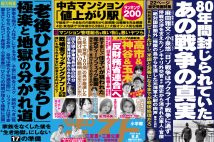児童が蹴ったボールを避けようとして男性が転倒し、後に死亡した事故で、子供の親の賠償責任が問われた事件が話題を呼んだ。「家族の監督責任」はどこまで問われるべきなのか。ベストセラー『家族という病』(幻冬舎新書)著者の下重暁子氏に話を聞いた。
* * *
まず申し上げておきたいのは、被害者が声を上げることができるということは、社会が成熟したということ。訴訟という道を確保する事自体は非常に重要なことです。 その上で、偶発的な事故にまで執拗な悪者探しが行われるのはおかしい。子供も認知症のご老人も社会が一緒になって保護するものであり、家族に24時間監督するのを強いることは酷です。
それでも家族だけが糾弾されてしまうのは、日本の社会において家族というものが特別視されているから。欧米では個が確立していますが、日本の社会では家族が重んじられます。例えば家庭内で妻が夫を「お父さん」と呼んで夫が妻を「お母さん」と呼び、名前を呼ばないのは、家族には個人ではなく、父、母、兄弟といった「役割」が求められているからでしょう。
家族どうしで、役割を超えた個人として接することは少なく、結局、それぞれの役割を演じている家族のことを一番理解できていなかったりする。良くも悪くも、日本人は「家族」という形を重んじます。だからそれを守るために必死になるし、家族同士本音でぶつからないということも起こる。
そのまま問題なく過ごせる場合もありますが、多くの場合遺産相続など後になって衝突する場面が出てきます。自分の都合のいいようにお互いを解釈し続けてきたぶん、修復不可能になったりするんです。個人主義ではなく家族主義社会の日本は、面倒見がいいとも言えますが、家族の庇護下にあって自立しにくいという面もあります。
最近、外国人と話していて一番驚かれたのが“振り込め詐欺”。家族のことを大事に思う感情はどの国も同じですが、「子供が他人に損害を与えた」と聞いて理性を失い、真っ先に「親である自分がなんとかしなきゃ」と考えるのは日本特有です。
外国であれば、心配はしつつ「ちゃんとサポートするから自分でなんとかなさい」となるでしょう。どこかで「家族が助けてくれる」「家族だから助けなきゃいけない」と考えているのが日本の社会なのかもしれません。
だから、家族に賠償責任を負わせようとする判例も出てくるのでしょう。しかし家族が最も大切だという人もこれには首をかしげたはずです。今のような多様化した時代、社会の枠の中で解決法を考えるべきで、そこで当然のように「家族」が出てくるのは、この国の病に他なりません。
※SAPIO2015年7月号