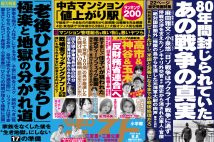いま国税庁は岐路に立たされている。数年前からIT長者などの「新富裕層」の海外移住が急速に進んだ。タックスヘイブン(租税回避地)のシンガポールでは相続税や贈与税、住民税がかからない。そうした課税逃れに対して、国税庁が打ち出した対策とは何か、ジャーナリスト、清武英利氏がレポートする。
* * *
税は国の根幹です。すべての国民に公平に課税しなければなりません。税収は教育や福祉など格差調整の役割を果たします。税は富の再分配の役割も担っています。
国の根幹を支える石垣こそが重要なのだ──。
所得隠しを取り締まる国税庁の職員は、入庁するとそう教え込まれます。いまも昔も国税庁は、1%のキャリアと99%のノンキャリアから成り立つ組織です。なかでも高卒の調査官は自分たちを「てんぷら」と呼んでいました。由来は諸説ありますがそのひとつが「叩き揚げ」ということのようです。
しかしいま高卒者が中心だった現場の職員にも学歴社会と高度情報化の波が押し寄せ、組織が変質しつつあります。また経済取引の国際化、申告数の増加にともなう事務の繁雑化などの影響で、十分な税務調査がこなせない状況に陥ってしまいました。
税務調査の対象となる法人や個人事業者などのうち、実際に税務調査が行われた割合を「実調率」と呼びます。平成21年度の法人実調率は4.6%。個人実調率はわずか1.4%に過ぎません。平成元年度と比較すると法人、個人ともに実調率は約2分の1に低下しているのです。
何よりも問題となっているのが、近年加速した課税逃れが目的の海外移住に対して有効な対策を打ち出せなかったことです。