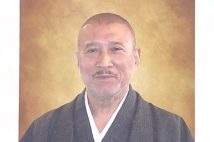「市ヶ谷のマザーテレサ」と呼ばれる秋山正子さん
◆看取りの文化を広げていきたい
小笠原:長く続く訪問看護ステーションには医師や看護師をコーディネートできる人が大抵1人はいます。どのお医者さんが合うのかも訪問看護師さんはよく知っています。
秋山:小笠原先生はもともと僧侶でいらっしゃるし、生きる、死ぬということについては独自の哲学をお持ちです。でも、先生のようなカリスマではない、地域の開業医のかたで在宅の看取りを体験されるかたが全国で少しずつ増えています。私たちのような訪問看護師やベテランのケアマネジャーが、医師、訪問看護師、介護の人のチームを作ればできるんです。
小笠原:患者さんやご家族のことも理解しているのが、地域のかかりつけ医です。「家で最期を迎えたい」という患者さんの願いを叶えるために、モルヒネなどの使い方に困った時には、訪問看護師、薬剤師、あるいはほかの医師に教えてもらえばいいんです。患者さんや家族の願いが、かかりつけ医を育てるんですよ。
秋山:ある看取りの現場で、ろくに挨拶もしなかった中学生の男の子が、おじいちゃんを見送ったあと、それを手伝った私たち看護師に「お世話になりました」とお礼を言ってくれたことがありました。やっぱり人の死は何かを変える力を持っています。おじいちゃんはこんなふうに家で亡くなったということを次の世代に伝えて、看取りの文化が引き継がれていくといいなと思っているんです。
小笠原:そうですね、特に子供は人の死を知ると大きく変わっていきます。それから、人の生き方・死に方をいちばん間近で見ている看護師の言葉は重い。『なんとめでたいご臨終』を読んで死が怖くなくなったという人もいらっしゃいます。「朗らかに生きる、笑顔で死ねる」、そんな看取りの文化を、同志としてともに広げていきたいですね(笑い)。
■撮影/太田真三
※女性セブン2017年8月3日号