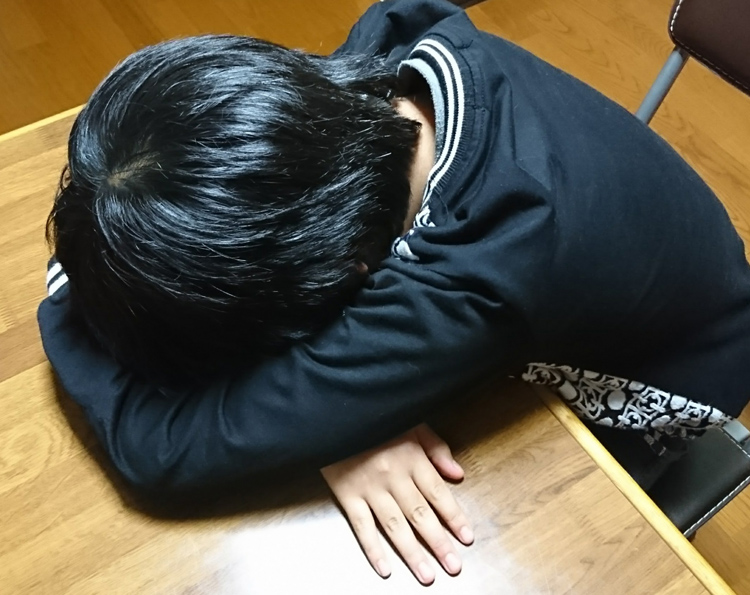中学受験で心身ともに壊れてしまう子どもが急増
◆パフォーマンスゴールと自尊感情
2016年に名古屋市で父親が中学受験に挑んでいた小学6年生の子どもを刺し殺すという事件がありましたが、これも、過度な親の受験教育・受験思考から、親の“心の暴走”と見ることができます。
一方、親の過剰な干渉や指導による反動が間違った方向に出てしまう子どももいます。2008年6月に東京・秋葉原で無差別殺傷事件(通り魔殺傷事件)が起こりました。当時25歳だった元派遣社員の男(加藤智大死刑囚)の犯行でしたが、彼は地元の進学校に進むも高校時代に成績不振に陥って挫折します。その後の調査で、犯人の母親がかなり教育熱心で厳しい親であることがわかりました。
犯人は、自己否定感に陥り、将来を悲観して通り魔という暴挙に出ます。親の意のままに育ってきた子は、周囲からは実に「いい子」なのですが、思春期になり、自分を見つめ直していく過程で、自らのゴールを模索し始めます。不登校になる生徒の多くに、こうした「いい子」の存在があります。思春期に至る過程で自己への渇望があるように思います。
◆その先にある子どもの心の崩壊
しつけと虐待の違いは、実にはっきりしています。自分の考え方に従わせる行為そのものは指導でもなければしつけでもありません。それは、服従であり、飼育と言います。
コントロールすべきは父親自身の行動や感情で、命令や、時に暴力を用いて従わせること自体をしつけとは決して呼びません。子どもの良き伴走者であるべき父親が、社会で活躍する手本となるべき父親がとるべき行動ではないと思います。自分の描く夢のゴールを、さも、子ども自身が望むゴールと勘違いしている。子どもにとっては、自分自身を見出したゴールではないのです。
子どもたちには、中学受験の先にもたくさんのゴールがあります。それぞれが次のステップとなるよう、学ぶためのゴールです。親は人生の先輩として、子どもの先を歩んでいます。だから、子どものためと思い、自らが子供の人生設計をしてしまうのでしょう。しかし、場合によっては、その道は「これで良いのだろうか」と自分自身で歩まされてきた道かもしれません。たとえ過去において成功例であったとしても、多様化する今の時代にはそぐわずに通用しないパラダイムになっている可能性が大きいのです。