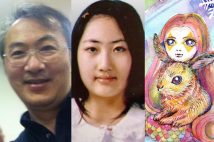國保監督は、選手の健康に気を遣いながら、エースやレギュラーに頼らず、全ベンチ入りメンバーで勝利を目指す戦い方を標榜する。それは盛岡第一高校を卒業後、進学した筑波大学野球部で学んだことが基になっている。
「恩師の川村卓監督(筑波大)には、長いリーグ戦の中で、(レギュラーの)9人に頼らず、控え選手も同じように試合に向けて準備して、苦しい状態の試合終盤や、公式戦の日程が進んだ段階で部員全員で頑張るというスタイルを学びました」
そして、大学卒業後にアメリカに渡り、独立リーグを経験したことが、投手の肩やヒジへの負担を軽減し、登板間隔を十分に保ちながら起用していく采配へとつながっている。
それでも國保監督は、昨夏以降、あの決断が正しかったのか、それとも間違っていたのか、自問自答する日々を送ってきた。「答えは見つからない」と私の取材で打ち明けた。その日の取材では、昨夏の岩手大会の準々決勝のことも振り返っていた。久慈との準々決勝で、國保監督は佐々木を起用しなかった。延長戦までもつれた末に大船渡は辛くも勝ちを拾ったが、あわや敗退の危機だった。
「もし朗希が投げずに最後の夏を終えることになったら、選手に悔いは残ったんじゃないか。あなたはそう書かれていましたよね。おっしゃる通りで、あの試合で負けていたら納得できなかったと思います。しかし、敗退の危機に陥る度にエースを登板させていたら、全試合でエースを投げさせなくてはいけなくなる。どこかでエースを投げさせないという試合は、今後必ず出てくると思います」
佐々木朗希の登板は日本中の注目を集めた
公立校はどうすればいいのか
昨年の騒動の直後に開幕した甲子園では、エースナンバーを背負った投手に頼らず、継投で勝ち上がるチームが増えた。猛暑の過密日程のなかで、複数投手を育成し、ベンチ入りメンバー総出で頂点を目指していく傾向は今後強くなり、スタンダードとなるだろう。昨夏の優勝校である履正社や大阪桐蔭、関東の日大三や東海大相模など強豪私立は既に、そうした戦い方を前提に選手のスカウティングに力を注いでいる。
だが、一昨年の甲子園準優勝校である秋田・金足農業や大船渡のような地方の公立校に、能力の突出した選手がいたら、どうしても個の力に頼らざるを得ないだろう。