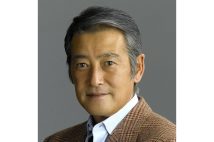財前も丙午の女性。「バブルの頃はとにかくお金持ちがモテていました(笑い)」(写真/本人提供)
丙午は出生数が少ないので、そもそも競争相手が少ない。そのうえバブル経済の恩恵があったため、彼女たちは就職活動でとことん有利だった。この頃山梨県の大学に通っていた漫画家の西炯子さんも追い風を感じていたようだ。
「当時の女子大生は、20~30社から内定を得ているのが普通でした。卒業間際に大企業が300人の追加募集をすることも。山梨がそんな感じだったので、東京はもっとすごかったんじゃないかな。就職先を選ぶ際も、『友達が○○に決めたから、一緒に行くの』という理由であっさり決める子が結構いましたね」(西さん)
大学を出た女性は「家事手伝い」という名前の花嫁修業をするか、そのまま結婚をするもの──そんな価値観は、その頃からガラリと変わった。
「私が大学を卒業する頃は、『結婚したら負け』という意識がありました。私たちは、女性が初めて社会で当たり前に働くようになった世代で、仕事で男性や同期と競うことがかっこいい生き方とされていた記憶があります。子供をつくらない共働きの夫婦を指す『DINKS』という言葉が流行したほどでした」(西さん)
2003年にベストセラーとなった『負け犬の遠吠え』(講談社)の著者である酒井順子さんも、丙午の女性だ。彼女は大学卒業後の1989年に総合職で博報堂に入社した。
「この本では、『30才以上・未婚・子ナシ』が“負け犬”とされた印象が強いかもしれないが、本質はまったく逆のところにあると思います」
と白河さんは言う。