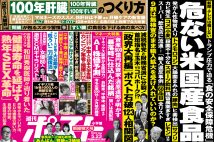大豆を原材料としたプラントベース・ミートを試食する河野太郎規制改革担当相(当時、2021年9月、時事通信フォト)
大豆イソフラボンの過剰摂取で乳がんに
代替肉の主な原料である大豆は、日本人にとってなじみ深い食材だ。しかし、世界的に見ると大豆を日常的に食べる国は珍しく、多くの国では、大豆は家畜の餌や燃料として用いられている。こくらクリニック院長の渡辺信幸さんが言う。
「日本では1871(明治4)年まで約1200年にわたって、肉食が禁止されてきた歴史があります。さらに第二次世界大戦中は、肉食を含めた多くの欧米文化が禁止されていました。日常的に肉を食べずに、大豆からたんぱく質を摂取していた食生活の名残が現在も続いているのです」
豆腐、納豆、みそ、豆乳など、日本人はすでに大豆を豊富に摂取している。さらにそこへ、肉を大豆ミートに置き換えると、大豆イソフラボンの過剰摂取になりかねない。
「大豆イソフラボンは『植物エストロゲン』ともいわれ、女性ホルモン類似の物質です。食品安全委員会によると、乳がんの発症や再発リスクを高める可能性があると報告されている。また、生殖機能が未発達な小児・乳幼児に対しては、大豆イソフラボンの摂取は推奨されていません」(渡辺さん)
垣田さんも言う。
「世界では大豆イソフラボンによる乳がんリスクは問題視されていない。それは安全を示すのではなく、日本ほど大豆を消費している国がほかにないため論じられていないだけです」
河野太郎規制改革担当相(当時)が試食した代替肉を使った料理
なお、朝食に納豆1パックと豆腐のみそ汁を食べたら、1日分の大豆イソフラボンをほぼ摂取している。さらに、代替肉には、食の安全に疑問が残る「遺伝子組み換え大豆」の問題もある。
「世界では遺伝子組み換え大豆の生産が増えており、総栽培面積の8割を占めています。輸入大豆はほとんどが遺伝子組み換えだと考えても間違いではない。今後、流通が拡大する大豆ミートに、遺伝子組み換えではない大豆が使用されることはかなり難しいでしょう」(垣田さん・以下同)
フランス・カン大学の研究チームが行った実験によると、遺伝子組み換えのコーンを食べ続けたマウスは、非遺伝子組み換えのコーンを食べ続けたマウスと比べ、約2倍もがんの発生率が上がり、早死にすることがわかった。
「輸入大豆では、収穫後に劣化、腐食を防ぐために使われるポストハーベスト農薬の問題もある。がんの原因になることが指摘されています」
積極的に食べるべきか、検討が必要だ。