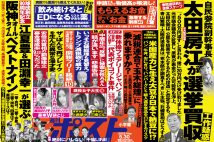1975年の夕食。生鮭のフライ(ゆで野菜つき)、蒸し鶏と絹さやの梅あえ、ピーマンとじゃこの炒めもの、しめじと玉ねぎのカレー風味ミルクスープ(出典『東北大学 日本食プロジェクト研究室の簡単いきいきレシピ』世界文化社刊。イラスト/いばさえみ)
当時の中流家庭では、肉料理といえば、ステーキ、シチュー、豚のしょうが焼き、そしてすき焼き。もっと庶民的なものでは、コロッケやメンチカツが日常的な洋食の代表格となった。
1975年を境に肉の摂取量は右肩上がりに増え続け、2015年には1日90g近く摂取している。一方で魚の摂取量はじわじわと減っており、2006年には、肉の摂取量の方が多くなる。1975年の「魚:肉=8:3」の割合が、もっとも健康にいいということだ。ではなぜ1975年に急激に肉食が増えたのか。
1975年といえば、高度経済成長がひと段落した頃。食文化史研究家の永山久夫さんは「この頃は誰もが明るく、プラス思考だった時代」と語る。1932年生まれで、今年で90才になる永山さんは、1975年当時は43才だった。
「日本の食文化は、敗戦を機に変わっていきました。進駐軍のアメリカ人と自分たちの体格や健康の差に驚き、その違いが食生活にあると気づいたのです。“おいしくて力がつく”と、日本人も少しずつ肉を食べるようになっていきました」(永山さん・以下同)
外食産業の登場も、日本人に洋食を定着させるきっかけとなった。すかいらーく、ケンタッキーフライドチキンの1号店の誕生は、大阪万博のあった1970年。翌1971年には東京・銀座にマクドナルド1号店が進出する。
しかし、肉ばかり食べていても体によくないと考えるようになった日本人は、従来の和食の欠点を修正しつつ、日本人向きの独自の食べ方を編み出し、それが一般家庭にも浸透していく。
「試行錯誤を重ねて日本人がたどり着いたのが“野菜と一緒に煮る”ことです。1970年代に出版されて当時大ベストセラーとなった『最新家庭料理全書』というレシピ本には、鶏肉、豚肉、牛肉を野菜と煮込んだ料理が多い。肉じゃがや豚汁は、いわば肉と野菜のスープ。和+洋のいいとこ取りの、日本食の傑作です。根菜類の煮物は『煮菓子』とも呼ばれ、来客をもてなすときにお菓子のように提供していました」
そして、卵を頻繁に食べるようになったのもこの頃。高度成長期には、当時、子供たちに人気のあった3つを集めて「巨人・大鵬・卵焼き」と言ったほどだ。
「卵の生産量、消費量ともに、1970年代は増えています。こうして、動物性たんぱく質の摂取量が増えていきました」