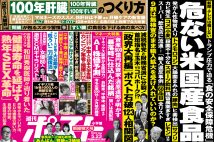39歳の放哉。神戸・須磨寺大師堂の前で(写真提供/鳥取県立図書館)
「字数の収まった人生」からズレていった放哉
放哉は、社内での人間関係がうまく行かず、酒に溺れて欠勤を繰り返すようになり、役職を解任された後、退職する。
再起を図って、日本統治下の韓国に設立された朝鮮火災海上保険に支配人として赴任したものの、再び酒で失敗。さらに肺病(肋膜炎)に冒されてしまい、日本へ帰国を余儀なくされる。さらに妻とも離婚して無一物となり、寺男や堂守などをしながら句作を続ける「独居無言」の生活を求めるようになる。
最期は、小豆島(しょうどしま)霊場五十八番札所・西光寺の奥の院「南郷庵(みなんごあん)」に移り住み、お遍路から受ける金銭と俳句仲間からの送金で細々と暮らした。
放哉が住んだ南郷庵。終の住処となった(写真提供/鳥取県立図書館)
28歳の時に初めて放哉の全句集を手にして以来、折に触れて何度も読み返しているという又吉直樹氏は、放哉の生き方をこう見ている。
「放哉は賢くて優秀な人だったから、制度の真ん中を歩もうと思えば行けた可能性がある。だから、有季定型の俳句のような、ちゃんと字数の収まった人生を送れる人だったかもしれない。でも、それが破調していくというか、ズレていった。そういう人が、五七五の俳句をきっちり収めるのも面白いんですけど、それはやっぱり崩すんでしょうね。そこに、不思議はないですよね」(又吉氏/以下同)
放哉の句と人生に、又吉氏はつながりを見たという(撮影/国府田利光)
又吉氏は、繰り返し放哉の句を味わううちに、“定型の破壊者”といったイメージから、実際の人生とのつながりが見えてきたという。
「最初に放哉の俳句を読んだときは、パンクスやと思ったんです。俳句を破壊しようとしてるのかなと。すごいかっこいいなと単純に思いました。
ところが、何度も読み返しているうちに、定型ではない形で、自分の俳句を実現させようとしていたのかなと思えるようになったんですよ。自由律俳句という形式と、放哉の人生がつながっているように見えてきたんです」