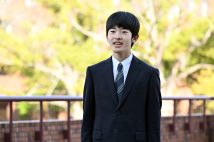自ら田植え機のハンドルを握る(ステッカー提供)
新潟県へ通い、そして抱いた「日本で野菜が買えなくなるかもしれない」危機感
彼女曰く、当時は価値観が狂っていて、とにかく人よりも目立つ生活をすることがアイデンティティになっていたそう。
「いいバッグ、いい洋服を追いかけていた自分も頑張っていたんですけどね(笑)。ただ長期間、新潟県へ通ううちに、そんな価値観も変わりました。農業そのものが高齢化によって、人手不足で危機にあることに気づいたんです。私がいた町でも、たったの10数世帯しかなくて、そのうち農家はごくわずか。最年少の方が65歳ですよ? 新潟は雪解け水でおいしいお米が育つのに、このままでは日本でふつうに野菜が買えなくなるかもしれない。この危機感が起業につながりました」
2023年の春以降、特に深刻化した全国的な卵不足の問題を例に挙げて、小林は話を続ける。
「あのとき、突然、世の中から卵が消えた。急に卵の値段も高騰して驚きましたよね。でも野菜も同じように突然買えなくなる可能性は十分あります。だって次を担う作り手がいないんですから。それを防ぐために、生産と消費の間でSDGsの必要性が叫ばれていて、あの17項目があるんです」
スーパーへ行けば当たり前のように野菜が買える日常は、いつかなくなるかもしれない。小林は皆がそんな状況から目を背けているように感じるという。生産者と消費者が互いに尊重しあう仕組みが作れないかと、情報収集が始まった。まず取り組んだのは、どの業界でも問題視されている人手不足の解消だったそう。
「野菜も同じように突然買えなくなる可能性は十分あります」(ステッカー提供)