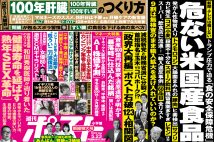米ラスベガスにある「ジェンダー・ニュートラル・トイレ」(イメージ、dpa/時事通信フォト)
2023年7月に経済産業省で、トランスジェンダーの職員が「女性用トイレが使えないのは不当だ」として訴えた裁判で最高裁が「トイレの使用制限は違法」と判断している。
「そういう特定の社員しか使わないオフィスのトイレなら教育して『そういう方も使う』でトランスジェンダーの方に配慮できるのでしょうけど、お店とか不特定多数が使うトイレでそうはいかないですよ。これ、逆に聞きたいのですけど、女性用トイレを使いたいって男性が来たとして、その男性が『自分は女性である』と主張するなら使わせないと差別になるんですかね。実際、他の女性のお客様は納得しないですよ、本当に大問題だと思います」
彼は差別の意味で言っているのではなく、現場で今後「男性の姿で男性器のついている女性と称する人物」が女性用トイレを使うことに対処する場合どうすればいいか」「他の圧倒的多数の女性客の意見をどうすればいいのか」という話をしている。トランスジェンダーなのかどうか、それを現場が判断するには無理があると。今回差し戻しとなった問題もあるが、それも含め、こうした声を現場のエッセンシャルワーカーが無視することは「難しい」と。
都内ターミナル駅のレディースブランドショップの店員もまた「難しい」と語る。
「理念はわかりますけど難しいです。プレゼントや女性の代わりに取りに来る男性の方もいらっしゃいますから店内は構いませんが、試着とか試着室の使用はお断りしています。差別とかでなく、無理ですよ」
直接的な言及は避けていたが、「難しい」「無理」が現実なのかもしれない。
本当に難しい問題、誰もが多かれ少なかれ「自分ごとと他人ごと」を分けて社会を生きている。そうした社会で、それまでの社会倫理と乖離した理想と現実が、より分断を生んでしまう。男なのか、女なのか、男であって女、女であって男、男の場所、女の場所、すべてが合致する社会ではないという現実に、「それは不可能ではない」という理想が空から降って来る。他の国はともあれ、この国ではそうだ。