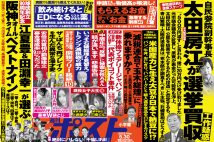2020年に駅前広場に移築された旧国立駅舎(2020年4月撮影:小川裕夫)
カナダでは、各州政府が森林を管理・所有している。そのため、州ごとに森林に対する決まり事などは異なる。細かな違いはあるものの、どの州政府も森林を大事に扱い、貴重な財産と捉えている。
そんな貴重な森林から切り出された木材を、カナダは日本へ初輸出した。そのカナダ材によって、被災した東京・横浜は復興を遂げていく。それまで日本とカナダは外交上での付き合いがほぼ皆無だったが、木材初輸入が縁となり日本とカナダの友好関係は築かれていった。
カナダ木材で建設された三角屋根の旧国立駅舎
カナダから届いた木材で、初めて誕生した木造建築が1926年に開業した国立駅だった。国立駅は関東大震災で被災したわけではないが、ブリティッシュコロンビア州が東京の復興を後押しするために送ってきた木材をふんだんに使っている。
そうした過程を踏まえれば、国立駅は震災復興によって誕生した駅とも位置付けられる。カナダ材を使った国立駅舎は特徴的な三角屋根が人気になり長らく市民から国たちのシンボルとして親しまれてきた。
しかし、JR東日本は中央線の高架化工事を理由に国立駅舎の改築を決断。駅舎改築は、三角屋根の駅舎解体を意味した。それだけに地域住民の反発は強かったが、JR東日本は国立駅舎の解体を断行した。
駅舎の保存を求める国立市と地域住民は、ふるさと納税をはじめとした多くの手段を活用して資金を調達。工事の関係もあり、三角屋根の国立駅舎は一時的に姿を消したものの、2020年4月に駅前広場に戻ってきた。
駅前広場へと移築された三角屋根の国立駅舎は、部材の7割をそのまま再利用している。大正時代の木材が、そのまま活用できることには驚くしかないが、それほどカナダ材の品質が高いことを証明したともいえる。
カナダから日本へと輸出される木材は関東大震災の復興事業後も、日本の建築・土木業界には不可欠な存在になっていった。
しかし、高度経済成長期からバブル期にかけて東京・大阪といった大都市部では高層ビルが立ち並ぶようになる。それらのビルの多くは、鉄やコンクリートを多用した。
「一時期、カナダでも建物の高層化が顕著になり鉄やコンクリートといった建材が多く使われるようになりました。それでも住宅は引き続き木造が主流で、木造文化が強く残っていました。それは日本も同様で、世界の木造住宅の需要はアメリカ・日本・カナダの3か国で大半を占めています。近年は木造の技術革新によって、カナダでは高層ビルでも木を使うようになっています。日本でも高層ビルに木を使う傾向が強まっているので、今後もカナダの木材が日本の建物で多く使われることになるでしょう」(同)