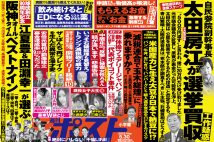じねんじょ列車の車内。美味しい郷土料理に舌鼓を打ちつつ、車窓を彩る里山風景を楽しめる(2006年撮影:小川裕夫)
運行開始から約40年続くグルメ列車
SLを運行することで新たな活路を見出そうとしている明知鉄道は、約25.1キロメートルの路線で、もともとは国鉄の明知線だった。
1985年に国鉄から切り離されて第3セクターとして再出発。その直後から、明知鉄道は需要創出の取り組みを開始した。1991年には飯沼駅、1994年には野志駅、2008年には極楽駅を新設。これら3駅が増えたことで、始点の恵那駅と終点の明智駅を含めて全駅数が11となった。
駅数が増えたことにより所要時間は長くなったが、駅間が短くなったことで使い勝手が向上した。
さらに、明知鉄道は1987年から「グルメ列車」の運行を開始。同列車は車内で地元の特産品である寒天を使った郷土料理が味わえることがウリで、観光客誘致と地域活性化の2つを目的にしていた。
寒天列車だけでは、リピーターを生み出しにくい。そのため、明知鉄道のグルメ列車はバリエーションを増やし、季節に応じた郷土料理を提供するようになる。
筆者は、2006年12月に「じねんじょ列車」を取材したことがある。車内で振る舞われた郷土食材の「じねんじょ」を使った料理に舌鼓を打ちながら、約1時間の里山風景を堪能した。また、じねんじょを振る舞ってくれた地元の料理店や住民団体の人たちに悲壮な表情はなく、話の節々から明知鉄道が愛されていることが感じられた。
季節ごとにメニューが変わるグルメ列車は、明知鉄道にとって継続的に観光客や来街者を呼び込めるキラーコンテンツになったが、これは明知鉄道という鉄道会社だけの力で成り立っているわけではない。沿線自治体や地元住民、経済団体といった多くの協力があってこそ高い人気を保っている。