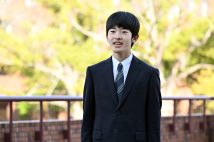カテリーナ氏のセルフ・ドキュメンタリー『私の故郷 ウクライナ』は2月23日に再放送予定(NHIKホームページより)
カテリーナさんの大学の友人は無人機やミサイルの音を聞き分けられるようになり、ミサイルの種類がわかれば自宅までの到達時間もわかると自分の変化を話した。「今ウクライナ人はみんな『小さな戦争の専門家』になっている」と。
5歳の男児を子育て中の女友達は警報が出ても子どもを怖がらせないよう遊びに仕立て上げるなど工夫していた。男の子は将来の夢を「戦闘機のパイロット」「戦車に乗る」と無邪気に語る。
圧巻だったのは高校の同級生の10年ぶりの同窓会だった。戦場で戦う2人の男性が参加できなかったが、後で1人が亡くなったという知らせが届く。誕生日が同じで毎年祝い合い、卒業式で手をつないでエスコートしてくれた青年だった。友人として直前まで同窓会の出欠を問い合わせていた彼の葬式を1か月の滞在中に経験する。彼女だけでなく、ほとんどのウクライナ人が戦争で身近な誰かを失っているという。
「何もかも上書きされるのが戦争だと感じました」
戦争という非常事態で「日常」が次第に浸食される姿。そのことを等身大の人間という立場から記録した貴重な映像だった。司会の鈴木奈穂子アナから「久しぶりの故郷で感じたことは?」と問われて声を詰まらせてカテリーナさんが語った言葉は次のとおりだ。
「今回、ウクライナに帰ってみて、正直にいって自分は今まで戦争が何なのかまったく知らなかったことを感じました。
戦争は、戦闘とか破壊とかだけではないからです。戦争とは、若者たちが自分の将来をまったく想像できないこと。若者が“将来”について聞かれると、涙が浮かんでくるのが戦争なんです。
あと、同級生が戦場に行ってその同級生と連絡を取るのが怖くなるのが戦争です。自分が言った言葉が最後の言葉になるかもしれないから。何を言えばいいかわからないから……。
戦争は、大切だった場所、幸せな思い出であふれていた場所がそこで大変なことが起きて、けっきょくそこで幸せを感じられなくなる。それが戦争です。上書きされていくんですよ。たとえば私の教室は、もう、ついさっきまで学生時代の楽しい思い出にあふれていた場所が、今は“私の戦死した同級生が勉強していた場所”になりました。
ですから、すべて“何もかも上書きされる”……。それが戦争だと強く感じました」