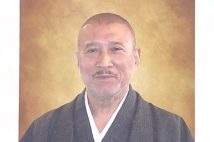小林誠司(時事通信フォト)
もっとスガコバの活用を
球史に残る名捕手であり名監督の野村克也氏は「優勝チームに名捕手あり」の言葉を残した。
昭和で言えば森氏や野村氏、平成以降ではヤクルトの古田敦也氏ら“不動の正捕手”が、攻守にわたって優勝チームを支えた。
その点、令和の巨人と阪神の起用法は往時と大きく異なる。1980年代の広島カープで正捕手として活躍した達川光男氏はこんな見解を示す。
「今のピッチャーは分業制です。とくに試合後半は1イニング交代でいいから強い球を投げさせ、継投で勝つ戦略を取るチームが多くなっている。加えて昔より“投高打低”で打者に比べて投手の力が高いことから、キャッチャーに求められる役割としてリード力よりキャッチングの能力や投手に気持ちよく投げさせられるかどうかの“相性”のほうが重要になってきている。だから正捕手が定めにくい。ややこしい時代になりましたよ」
相対的に投手の力が増している時代にあって、巨人と阪神の正捕手問題は今後どうあるべきか。達川氏はこう言う。
「阪神の岡田監督は以前はなぜか梅野のほうを使いたがったが、今は2人が切磋琢磨していい方向に働いている。これを続けていくのがいいのではないか。
巨人は菅野と小林を組ませたのが阿部監督の名采配ですが、問題は大城。リードもいいし、肩も強いが、足首や股関節が硬いから構えが高くて投手の印象がよくない。少しずつ岸田をメインにしていって、大城は一塁手で起用していくかたちがいいのでしょう」