1945年8月20日、満洲のハルビン市内を進むソ連兵(写真=SPUTNIK/時事通信フォト)
小泉:日本人の心のどこかに“裏技としてのロシア”みたいな感覚があると思いませんか。世界は表向きには英米に牛耳られているが、ロシアとつながれば巧みにバイパスして切り抜けられるんじゃないか、と。
麻田:たしかにありますね。実際、1945年2月のヤルタ会談にスターリンが出席し、敵対心を向けられていることを察する人は日本にもいた。シベリア鉄道での武器や兵士の輸送を目の当たりにした陸軍将校も、戦争準備が始まったと分かっていた。にもかかわらず、軍内部に「ソ連の対日参戦防止」という考え方が浮上すると、外務省も一緒に仲介を頼む方向に流れてしまうんです。
小泉:麻田さんは前著『日露近代史』で、19世紀半ばの開国当時の日本でも、指導者が「アメリカよりロシアのほうが話せる」と感じていた様を書かれています。そんな感覚が日本にはあったけれど、約1世紀後の日ソ戦争でハッキリ裏切られたとも映りますね。
麻田:しかも日本陸軍には「資本主義の英米と共産主義のソ連は必ず衝突する」という、ある意味で冷戦を先取りした認識もあった。しかし、その「ソ連とは話ができる」という感覚が間違った判断につながりました。
小泉:現在のプーチンもそうですが、権威主義国家の指導者は簡単に「ノー」と言わないんですよね。「ノー」と言ったらそれが絶対になってしまうから、こっちが無茶な期待を抱いていても、向こうは頭ごなしには否定しない。他方、こっちは「否定されなかった」と期待を持ってしまう。
(第2回に続く)
【プロフィール】
麻田雅文(あさだ・まさふみ)/1980年、東京都生まれ。成城大学法学部教授。専門は東アジア国際関係史。『日ソ戦争』にて読売・吉野作造賞受賞。他に『シベリア出兵』など著書多数。
小泉悠(こいずみ・ゆう)/1982年、千葉県生まれ。東京大学先端科学技術研究センター准教授、軍事評論家。専門はロシアの軍事、安全保障。『「帝国」ロシアの地政学』『ウクライナ戦争』『オホーツク核要塞』など著書多数。
※週刊ポスト2025年8月8日号



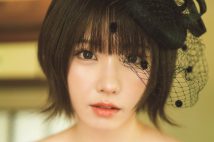





](https://www.news-postseven.com/uploads/2023/02/24/jiji_renzokugoto-214x142.jpg)



