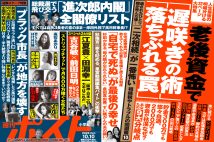社会保障費増大の落とし穴
「2040年度の社会保障費は、1.6倍になる」
そんなニュースが話題になったのは2018年のことだ。内閣府が発表した「社会保障の予測」を伝えたもので、各メディアで騒ぎになったのを覚えている人もいるだろう。
この試算によれば、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上になり、高齢化率は35%にまで増加。国民のおよそ3人に1人が高齢者となり、それとともに社会保障費が190兆円にまで増えるという。“1.6倍”という数字は各所に衝撃を与え、今もなお日本崩壊の理由として持ち出されることもある。たしかに、このペースで社会保障費が増えれば、ほどなく資金は尽きるはずだ。
ところが実際には、ここにもまた数字のとらえ違いが見られる。社会保障の重さを、支払いの総額から見ても意味がないからだ。医療費や年金などに使われる資金は、たんに高齢化のせいだけで増えるわけではない。時間がたてば経済は成長するし、それだけ物価も上がる。物の値段が上がれば、医療、介護、薬に必要なお金も増えるから、同じサービスを提供するだけでも支出は増える。 経済の成長とともに、社会保障の額が膨らむのは当たり前だ。
たとえば、月収20万円で家賃10万円の家に住む人と、月収100万円で家賃20万円の家に住む人を比べてみよう。単純に見れば後者のほうが出費が多いが、だからといって「月収100万円の人は、月収20万円の人よりも、2倍の家賃を負担しているから大変だ」という人はいないはずだ。これと同じで、支払いの総額だけを見て「未来の出費は1.6倍だ」と騒いだところで得られるものはない。そのため、社会保障の正しい重さを理解するために、経済学では「GDP比」が使われる。
これは社会保障で使う金をGDPで割った数字で、「2024年にはGDPの25%が社会保障に使われる」といった形で評価する。簡単に言えば、福祉に支払う額が、今の経済力に見合ったレベルなのかどうかを判断する指標だ。この指標のほうが優秀なのは当たり前だろう。月収20万円で家賃が10万円の人は、収入の50%を住居費に使っている。これに対して、月収100万円で20万円の家に住む人は全体の20%しか出費していないのだから、どちらのほうが負担が重いかは明らかだろう。社会保障費の問題も、これと同じだ。
不安を煽る「悲観論」
それでは、未来の成長を織り込んで計算したら、結果はどう変わるのか。
内閣府は、2028年からの名目GDP成長率を0.7%台程度として計算し、2024年には名目GDPが790.6兆円に達すると試算している。名目GDP成長率を0.7%台とするのは、デフレ期のトレンドを踏襲しており、十分に慎重な見積もりだと言える。
これをもとにGDP比を計算すると、2018年が20.8%で、2040年が23.5~23.7%となる。倍率にして1.14倍ほどの増加でしかない。今より支出が増えるのは確実だが、なんとなくイメージしていた負担感とは大きく異なるだろう。社会保障のような長期の制度設計は、GDP比で見ないといらぬ焦りを生む。