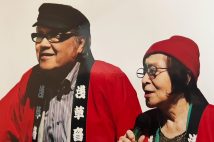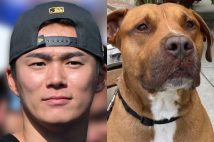雄大な自然の中を走る新型ロマンスカーのイメージ(画像提供:小田急電鉄)
かなりマニアックな相違点のようにも思えるが、2つの車体で1つの台車を共有する連接台車と、1つの車体に複数の台車が取り付けられているボギー台車を採用するボギー車では、構造以外にも多くの違いがある。たとえば、走行する際に発せられる「ガタンゴトン」というジョイント音が異なって聞こえることや振動の少なさなど、乗客の快適性にも影響する部分もある。
VSEが鉄道ファンや小田急ユーザーから絶大な人気を誇った理由も、乗り心地がスムーズだとされる連接台車が採用されたことが大きい。これから投入される新型ロマンスカーはボギー車を採用するが、白いロマンスカーVSEは連接台車の車両だった。構造上の大きな違いがあるのに、なぜVSE の後継と位置付けられているのか?
「新型ロマンスカーをVSE の後継と謳っているのは、EXEにはなかった展望車があるからです。ボギー車を採用したのは、連接台車の車両よりも一両に座席を多く確保できることや技術開発によってボギー車でも乗り心地が向上していることが大きな理由です」(同)
VSE一編成の座席定員が358名なのに対して、ボギー車を採用したGSE一編成の座席定員は400人。一編成で約50人の差は輸送効率を考えると大きい。
そのほかにも、ホームドアの整備を進めるためにドアの位置を揃えなければならないという事情がある。現役のロマンスカーとして走るMSEやGSEは、ボギー車を採用している。もし新型に連接台車を採用すると、ドアの位置がズレてしまう。こうした事情も勘案されて、80000形もボギー車になったようだ。
こうした台車まで気にするのは鉄道ファンゆえで、ライトユーザーにとって気になるのは、かつてのロマンスカーがウリにしていた“走る喫茶室”だろう。
「走る喫茶室」への期待
新幹線や特急列車などでもワゴンサービスによる飲食物の販売はされているが、ロマンスカーの車内では淹れたてのコーヒーをグラスで味わうことができた。また、サンドイッチなどの軽食も提供されるなど、レストラン・カフェに等しい飲食やサービスを受けることができるので、リッチな気分で鉄道旅行を楽しめた。
そうした上質なサービスを提供した“走る喫茶室”には根強いファンも多かったが、経済効率的はよくない。時代の流れもあり、小田急は2016年に“走る喫茶室”のサービスを終了した。その復活はあるのだろうか?
「新型ロマンスカーで”走る喫茶室”を復活させるかどうかについても、現在は検討中としかお答えできません」(同)
新型ロマンスカーが発表されたものの、現時点で不確定要素は多い。新型ロマンスカーが運行を開始するまで2年以上もある。それまで段階的に明らかにされていくと思われるが、新しいロマンスカーが箱根路を駆け抜ける姿を見られることを楽しみに待ちたい。