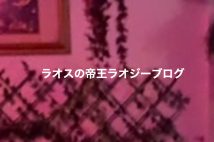ピンク地底人3号氏が新作について語る(撮影/朝岡吾郎)
〈京都市左京区静市にある黒いトンネル。その入り口付近の木陰に、アイドリング中のトラックが一台停まっている。シャッターの降りた荷台の暗がりでは、汗と涙で顔をぐちゃぐちゃにした全裸の僕が立っていて、そんな僕の前ではうんこ座りのカンザキさんが業務用のぶっといカッターで床にがりがりと絵を描いている。一体何の絵を描いているのかわからない〉……。
そんな、何があったかは知らないが、何かが相当に不穏なことだけはよくわかる場面から、京都を拠点に活躍する劇作家、ピンク地底人3号氏の初小説『カンザキさん』は幕を開ける。
幸い物語はこの場面から数行後、主人公の僕こと〈ノミ〉がその配送会社を辞めて10年が経った現在へと飛び、どうやら彼は無事に生き延びており、5歳の息子までいることが明かされるのだが、〈時折、僕はカンザキさんにとらわれてしまう〉〈カンザキさんとはまるで関係ないと思われるものに触れた時、カンザキさんはそこにいる〉というほど、その暴力は絶対的で身近なものでもあった。
同志社大学在学中に演劇活動を始め、現在は自身が作・演出を務める「ももちの世界」や他団体への戯曲提供でも注目される著者。近年では劇作家が小説を書くことは珍しくはなくなっているが、本作も「もし小説を書きたくなったら必ず連絡を下さい」という編集者の誘いに応じた著者にとって、人生初の小説であり、文芸誌掲載から程なく野間文芸新人賞を受賞するなど、早くも話題を呼んでいる。
「そういう思いもよらない提案があった時、僕は大体やりますって言うんです。ただし締切がないと書けないので、2か月後にお渡ししますって。それで、初めて書く小説は私小説に近いものにしようと決めました。
引きこもりやったのもホンマやし、鬱病で大学に行けなくなったのも本当の話。そんな時にたまたま演劇と出会って、他にできることもないから大学を出た後も演劇を続けてます。20代の頃は納棺師とか、経験値を貯めるために人がやらない仕事をいろいろとやって、家電量販店傘下の配送会社の仕事もその一環でした」
冷蔵庫や洗濯機を基本は2人1組で各家庭に届けるきつい仕事を主人公がそれなりに続けられたのは、最初のパートナーが〈ミドリカワさん〉だったからだ。
元々小柄で非力なミドリカワさんは、今では〈優れた配送員第一位〉にも選ばれるほど、努力家で優しい人。一方のカンザキさんは運転席を煙草の灰や食べかすで汚し、その悪臭を〈ピンクシャワー、サムライマン〉等々、何の香りかわからない芳香剤で悪化させた上に、殴る蹴るは朝飯前。そして延々続く〈禅問答〉のような会話に答え損ねたら最後、〈殺すぞぼけ〉と恫喝される。つまり、その日、誰の車に乗るかが彼ら新人の命運を分けるのだ。