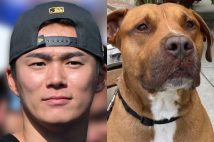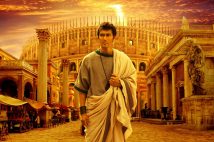だが1990年代になり、温度上昇により脳が破壊されるメカニズムや脳温がどのようにコントロールされているかの仕組みが解明され安全性を高めた現在の脳低温療法が現われた。当時、日大板橋病院で独自の脳低温療法を確立し、脳外科の権威として知られる医学博士の林成之氏が語る。
「1991年に初めて脳低温療法によって瞳孔散大状態の患者の社会復帰に成功しました。従来の治療方式では社会復帰が困難とされた重症患者が回復したという事例によって、世界的に注目されるようになりました」
林氏は細胞レベルまで患者のデータをリアルタイムに測定できるコンピューター管理システムを開発、さらに総勢140人のスタッフが24時間このシステムを支える態勢を整えた。脳温、脳圧、心内圧、心拍出量など72項目を常時チェックする研究を重ね、合併症が少なく、効果のある脳低温療法の条件を見つけ出した。
この治療法で死の淵から驚異の回復を遂げた人物がサッカー日本代表元監督のイビチャ・オシム氏だ。2007年11月、脳梗塞で倒れた当初は生命が危ぶまれたが、救急搬送された順天堂大学浦安病院で脳低温療法を受けて生還。手足にわずかな後遺症が残ったものの、病に倒れる以前と同じように数か国語をスラスラと話すなど、記憶や思考はほぼ完全に回復している。
2008年には愛知県の3歳児が氷の張った池に転落、10分以上も心肺停止状態になり、意識不明が5日間続いたものの、いち早く脳低温療法を施された結果、後遺症なく日常生活に復帰したことも話題になった。
※週刊ポスト2014年7月11日号