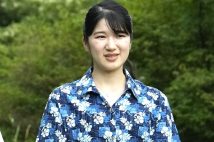さて、オリンピック観戦でも新たなアイデアが多数ある。
まずは「スーパーナビ」。眼鏡型のウェアラブル端末を掛ければ、観客席からでも競技を間近に見ることができる。望遠鏡の機能があるわけではない。競技場に複数のカメラを設置し、競技を立体的に映して眼鏡型端末に送信する。
そうすると、360度どの角度からでも臨場感ある競技映像を見ることができるのだという。サッカー観戦で、客席から応援しながら、選手同士のボールの取り合いを間近に、好きな角度で見ることができるというわけだ。
競技中以外でも、IT技術によるおもてなしを受けられる。スーパーナビによって、会場施設内の道案内を受けられる。トイレも場所だけでなく、混雑状況も分かる。会場内でのお弁当などの購入はスーパー扇子を使う。
こうした会場では、子供が迷子になることがままある。そこで「顔認証による迷子探し」のシステムも導入。入場時に希望者は迷子探しサービスを申し込み、子供の顔画像を登録する。
迷子発生時に、親が迷子センターに掛け込み、会場の監視カメラ画像から迷子を探しだす。見つけたら、近くの関係者に連絡し、迷子を保護するという。ちなみに、このサービスにあたっては、子供の顔画像を登録する際、家族写真の撮影や似顔絵をプリントアウトするなどのサービスを付け加えてはどうかとの提案もなされている。
顔認証は迷子探しだけでない。選手や競技関係者の顔画像を登録し、選手村やメディアセンターへの出入りに使う。近年、セキュリティ対策はどんどん厳しくなり、選手村に入るために何重ものチェックを受け、選手や関係者はうんざりしている。それを軽減するため、“顔パス”で出入りできるようにするというわけだ。
こうしたIT技術でネックになるのはバッテリーだ。そこで、観客席やメディアセンターなど大量の端末が使われる場所に、「ワイヤレス給電システム」を配備。何もしなくても、充電ができてしまう。
オリンピックの花・マラソンを想定したアイデアもある。「ミスト」だ。真夏の開催ということで、マラソンなどは「自殺行為だ」との声も挙がっている。そこで、水を霧状のミストにしてコースに撒くことで、選手や観戦者の熱中症を防ごうというもの。現在、国交省が散水システムを実証中とのこと。
ちなみにこの技術は、冬には融雪にも利用できるのだという。ソーラーパネルで稼働する路面散水コントロールセンターが、地下鉄の湧水などを利用し、マラソンコースを冷やす。
この他にもたくさんの夢のようなアイデアが満載。この政策提言通りになれば、2020年にはSF小説が描いていた世界が現実のものになるわけだ。
この提言は平井卓也代議士を委員長に31人の自民党議員が策定したものだという。ただ、メンバー議員の複数の事務所にデジタル・ニッポンに関する取り組みを聞いても「そんなの、ありましたっけ?」と言うばかり。
「どうしても国土強靭化の方に目が行って、こうしたデジタル系は理解されない傾向が強いんだよね」(自民党関係者)