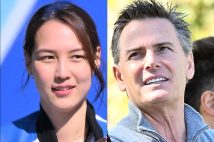そもそも授業計画を思いついたきっかけが、安保法制審議中の昨年7月に国会前の座り込みに教諭自身が参加し、そのときに感じた“熱気”を伝えるためというから、狙いは明らかだ。主権者教育とはほとんど関係ない世界史の授業時間に実施されており、学習指導要領ともほど遠い。
さらに問題なのは、政治的中立性を装っていることだ。例えば安保法案に関するデモについては賛成・反対の双方の立場のデモに言及しているが、授業の最後に、デモ行動のヒントとして自民党の憲法草案を批判する弁護士グループのホームページをさらりと紹介するなど、学校現場で求められる政治的中立からの逸脱は明らか。
デモの問題点を考える授業では、騒音や交通など周辺住民の生活への影響を指摘し、その上で「地域の理解と協力が必要」とデモの〝実践マニュアル〟ともいうべきアドバイスまで盛り込んでいる。この教諭にとって、主権者教育とは選挙で一票を投じるよりも「デモ」を行うことを意味するのだろうか。
【PROFILE】森下毅●1970年東京都生まれ。学校現場や行政機関に幅広い取材源を持ち、経済から教育まで幅広く取材、執筆している。
※SAPIO2016年8月号