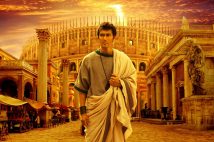尖閣周辺海域で中国漁船が海保巡視船に体当たり(2010年11月)
東アジアで米軍のプレゼンスが低下するなか、尖閣諸島周辺で日中が対峙すれば、史上初めて戦闘行為で自衛隊員の血が流れる可能性がある。1999年の能登半島沖不審船事件で”戦闘現場”に遭遇し、その体験を『国のために死ねるか』(文春新書)に綴った元海上自衛隊「特別警備隊」先任小隊長の伊藤祐靖氏は、「自衛官に死者が出る」ことの覚悟を国民に問う。
* * *
危険な任務に向かう隊員は、たったひとつしかない生命を賭して任務を達成しようとするが、それがすべてではない。祖国が正しいと信じたこと、断じて許容すべきではないと決めたこと、そしてそれを貫こうとする祖国の意思に自分の生命を捧げるのである。だから、命令する側は、隊員の生命を賭してまでなぜ、何を守ろうとしているのかを説明できなければならない。
1999年の能登半島沖不審船事件では、拉致されている最中の日本人を何が何でも奪還するという明確な国家の意思と任務の目的が見えていたが、2015年に成立した安保法制には「背後に米国の匂いを感じる」という声が少なくないし、私も不穏な感じがしている。
自衛隊の出撃とは、国家の命によってなされる武力の発動であって、災害派遣とは次元の違う行為である。それは、国家が国民の一員である自衛官に殺害を命じ、また、殺害されることをも許容させる行為だからである。だからこそ、国家の明確な「なぜ」「何を」「どれだけのリスクの範囲で守るのか」という合理的な目的に基づくものでなければならない。
国家が掲げる目的は、当然ながら国民の意思が大きく反映されたものであり、そうであるならば、懸念されるのは、左の端から右の端まで一気に振れてしまう国民性の存在である。