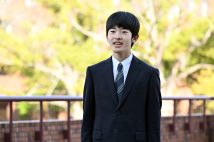踊り場からガラス扉越しに見た博物館動物園駅改札は、当時のまま残っている
“恩賜”と冠せられるように、上野公園は明治期に皇室の御料地だった。その後、東京市に下賜される。元御料地の下に電車を走らせるとなれば、簡素な駅舎をつくるわけにはいかない。京成は威信を賭けて駅舎を建築しなければならず、皇室の威光を示す荘厳なデザインが採用された。また、デザインだけではなく、使用された石材も高級品が選定されている。
「博物館動物園駅は屋根の部分にテラコッタ、壁面部分に岡山県で産出される万成石を使用しています」と説明するのは、京成電鉄経営統括部広報・CSR課の担当者だ。
テラコッタも万成石も、特に京成と縁はない。「おそらく、『皇室に失礼がないように高級石材を』という理由から選ばれたと思われます」(京成電鉄経営統括部広報・CSR課)という。
万成石は、ほんのりピンク色味のある特徴で、明治神宮外苑の中心的施設である聖徳記念絵画館や日本橋の三越本店にも使用されている。
1972(昭和47)年、上野動物園にパンダのカンカンとランランが来園して大フィーバーが巻き起こると、博物館上野動物園駅は人で溢れかえった。
しかし、博物館動物園駅のホームは総延長が4両分しかない。そのため、京成の利用者が増加して6両編成の電車運行ばかりになると、普通電車も通過する寂しい駅になってしまった。
無用の長物と化した博物館動物園駅は、1997(平成9)年に営業を休止。2004(平成16)年に正式に廃止された。
由緒ある駅だけに、廃止された後も駅舎は取り壊されなかった。NPOやまちづくり団体は、博物館動物園駅の遺構を再活用しようと模索した。しかし、安全上の理由から再活用にまで漕ぎつけることはできなかった。
博物館動物園の駅舎は、今年に東京都選定歴史建造物の指定を受けた。駅舎の歴史的価値が広く認められたわけだが、今年11月23日からは地元の台東区や京成電鉄、東京藝術大学で組織される上野文化の杜新構想実行委員会の尽力によって、長らく眠りについていた駅舎内部が一般公開される運びになった。
今回の一般公開はアート作品の展示といったイベントも兼ねており、期間は2019年2月24日までに限定されている。
鉄道ファンを対象にした公開ではないこともあり、残念ながらホームまで立ち入ることはできない。一般公開されるのは、駅舎入り口から階段通路、そしてきっぷ売場窓口だった階段の踊り場までだ。そこから先はガラス扉が設置されて進入できない。
期間も区域も限定されているが、ガラス扉越しに当時のまま残された改札を眺めたり、通過していく電車の轟音を聴いたりすることはできる。それだけでも、貴重な体験といえるだろう。