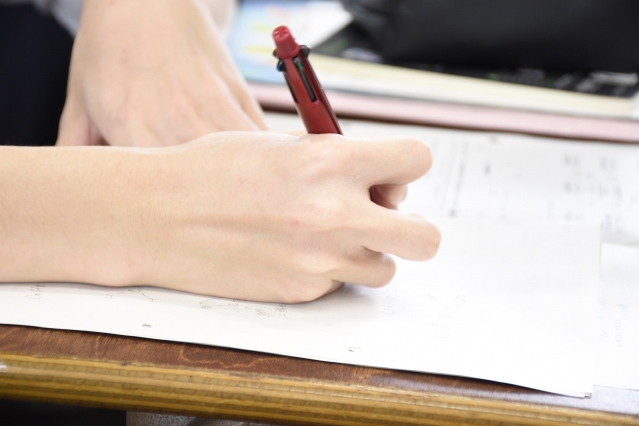「入れ替えのないリーグ戦のようなもの」
中堅校の名称には日東駒専(日本大、東洋大、駒澤大、専修大)、大東亜帝国(大東文化大、東海大、亜細亜大、帝京大、国士舘大)、関西では産近甲龍(京都産業大、近畿大、甲南大、龍谷大)、神桃追摂(神戸学院大、桃山学院大、追手門学院大、摂南大)などがあり、頻繁に使われている。
ただ、近畿大は大学のグループ分けについて、「入れ替えのないリーグ戦のようなもの」と評している。関西でいえば、京阪神(京大、大阪大、神戸大)、関関同立、産近甲龍、神桃追摂の順で、微妙な変化は起きているものの、何年経っても大学の入れ替えはないからだ。
高校や予備校の合格実績に使われる大学のグループ化
こういったグループ分けは、進路指導だけでなく、高校などで大学合格実績が伸びていることを表わす指標としても使われている。
保護者への説明で「MARCHは昨年より〇人増えました」などと結果報告するわけだ。だから、対象の大学が増えると、合格者数が増えるため、新しいグループ分けは使われやすくなる。
例えば、「早慶」は上智大の就職の良さと難化で「早慶上智」になり、そこに東京理科大を加えて「早慶上理」という言い方ができた。MARCHに学習院大を加えて「G─MARCH」もできた。この二つは最近、よく使われているようだ。
このように、今までどのグループにも入っていなかった大学を加えることは行われている。また、京都の進路指導教諭は「産近甲龍は京都では産近佛龍ということもあります。兵庫の甲南大までは生徒は行かず、地元の佛教大を選ぶからです」と言う。こういったローカルな呼び方もある。