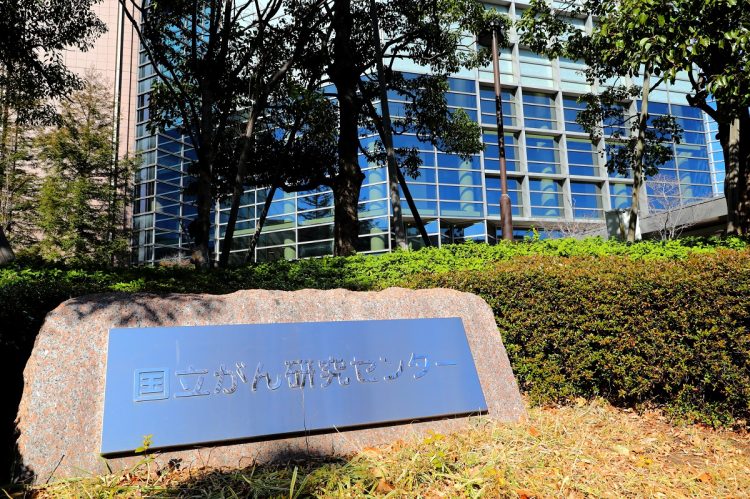がん研究センター(写真/アフロ)
加齢マウスの身体機能が改善
生存率を高め、“治るがん”にした薬とはどんなものなのか。
「例えば乳がんでは、抗がん剤の進化に加え、2020年には抗HER2薬『エンハーツ』が承認されました。乳がんをはじめ、胃がんや肺がん、大腸がんなどの表面に発現するHER2というたんぱく質を目印にがんを攻撃します。
エンハーツもそうなのですが、抗体に薬物を結合させ、抗体が狙った細胞や組織にピンポイントで薬物を輸送できる抗体薬物複合体(ADC)が続々と登場し、さらに生存率を高めることが期待されています」(室井さん)
エンハーツの適応拡大承認を取得した製薬メーカー「第一三共」の株価が高騰したことからも、注目度と期待値の高さがうかがえる。日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣範之さんも、がん治療薬の進歩についてこう話す。
「肺がんや胃がん、肝臓がんなどの生存率が伸びているのも、新しい治療薬によるものだと考えられます。特に大きいのは、2014年に初めて承認された『オプジーボ』をはじめとして、免疫チェックポイント阻害剤が次々に開発されていることです」
私たちの体は、免疫の力によって、がん細胞などの異物を体内から排除する仕組みを持つ。従来の抗がん剤は、がん細胞の分裂を抑えて増殖させないようにする働きだったが、免疫チェックポイント阻害剤は免疫システムを再活性化することで免疫細胞が、がん細胞を攻撃できる環境を作り出す仕組みだ。
2018年にはこの仕組みの発見とがん治療への応用により、京都大学の本庶佑名誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した。また、昨年11月には、オプジーボを加齢マウスに投与すると、体内の老化細胞が顕著に減り、身体機能が改善したという研究成果を東京大学と金沢大学のチームが発表。今後のさらなる使用拡大が見込まれている。コロナ禍に肺がんが見つかった会社員の男性(50代)がこう話す。
「コロナに罹った後、肺への違和感があり、後遺症かと病院へ行ったら肺がんが見つかりました。そのときに使用をすすめられたのがオプジーボです。免疫療法だというので、少し二の足を踏んだのですが、保険適用になっているということもあり思い切って治療に挑んだところ、手術をしなくてもがんが小さくなったんです。予後も順調で、お願いしてよかったと思っています」