●第四海軍燃料廠跡〈志免鉱業所跡〉(福岡県志免町)
1889(明治22)年に設立された海軍の新原採炭所に端を発し、艦船の燃料にする石炭を採掘した。1941(昭和16)年に第四海軍燃料廠に改組、1943(昭和18)年に高さ47.6mの竪坑櫓(写真)が竣工した。深さ430mの竪坑から採炭夫や石炭を移動させた竪坑櫓は現在、国指定重要文化財。近くにはボタ山も残る。
第四海軍燃料廠跡〈志免鉱業所跡〉(福岡県志免町)
●片島魚雷発射試験場跡(長崎県川棚町)
佐世保海軍工廠で製造される魚雷の性能テストを行なう発射試験場が、1918(大正7)年、離島だった片島に設置された。太平洋戦争開戦に伴って1942(昭和17)年には対岸に川棚海軍工廠が新設。海峡が埋めたてられて島は地続きになり、試験場にも探針儀領収試験場などが増設された。
片島魚雷発射試験場跡(長崎県川棚町)
●公益質屋跡(沖縄県伊江村)
沖縄本島の西に浮かぶ伊江島では、1945(昭和20)年4月16日に戦闘が始まり、米軍が海から艦砲射撃を繰り返した。庶民向けの金融機関だった「公益質屋」の壁に残る砲撃跡が戦闘の激しさを伝える。住民約1500人、日本兵約2000人が犠牲になった。
公益質屋跡(沖縄県伊江村)
●陸軍の境界標石(東京都渋谷区)
渋谷駅周辺には明治時代から終戦まで複数の軍事施設があった。駅至近の「TOHOシネマズ渋谷」の裏手には「陸軍用地」と刻字された境界標石が残るが、気に留める通行人は皆無に等しい。近くにはかつて陸軍刑務所があり、二・二六事件を首謀した青年将校たちが処刑された。
陸軍の境界標石(東京都渋谷区)
写真/太田真三
※週刊ポスト2025年8月8日号






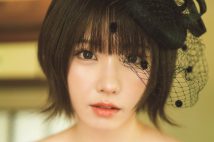





](https://www.news-postseven.com/uploads/2023/02/24/jiji_renzokugoto-214x142.jpg)



