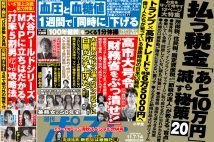冬眠をしないクマの出現が恐れられている(イメージ)
全国に広がる熊害、クマの天敵でもあったニホンオオカミの絶滅から100年以上、日本の生態系の王として君臨するクマが一部専門家の指摘の通り、人を恐れるどころか人を簡単に食べられる肉と認識し始めたというのか。環境保護、動物保護と人間の保護、これから冬到来を前にますますクマは活発に餌を求め続ける。
80代男性はこうも懸念する。
「冬は冬で『穴持たず』と呼ばれる巣ごもりしない、できなかったおかしなクマがいる。そういうのは腹減ってるし頭が変になってるのか知らないが、本当に怖いんだ。大事なのはクマか人間か、俺からすればそんな選択はおかしいと思うよ」
胎児を含め7人を殺した三毛別のヒグマは「穴持たず」だった。ヒグマの恐怖はもちろん、ツキノワグマでも10月8日に発見された北上市の男性は頭と胴体が別々に転がっていた。
2メートルを超えるヒグマに比べれば小型のツキノワグマであっても、とくにオスのパンチ力と鋭い爪、噛む力は人間など相手にもならない。臭覚も鋭く執着心も強く、そして賢い。学習能力が高く、人は強くて怖いと覚えることもあれば、人は弱くて美味しいと覚えることもできるとされる。
連日報道される熊害、各社いずれも決して大げさに伝えているのでなく事実であり、多くの被害者を出している。私たち人間が食べられる側であることを思うと、「大事なのはクマか人間か」という、人生の大ベテランの言葉は重い。
人間を襲い続けるクマ、山に入らなければいいという話でもなくなってしまったいま、共生の模索を続けるのは当然として、ひとまず高市早苗新首相による政府として一歩踏み込んだ、さらなる「人間保護」のための熊害対策に打って出るしかないように思う。
●日野百草(ひの・ひゃくそう)/出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュを手掛ける。日本ペンクラブ広報委員会委員。