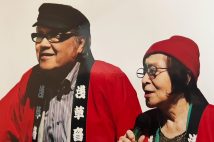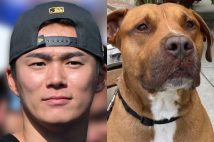保線作業は線路のあるところすべて、山の中へ行く必要もある(写真提供/イメージマート)
今年度はクマの出没が突出している。分析する立場にはないとはいえ、安全に列車を運行しなければならない使命を追うJR東日本は、どんな対策を講じているのだろうか?
「鉄道では定期的なメンテナンス作業は欠かせませんが、保線などの作業員は山間地に足を運びます。身の安全を図るため、クマ撃退のスプレーやクマ除けの鈴などを持たせています。また、奥羽本線や田沢湖線、羽越本線の一部区間ではクマの出没状況を踏まえて忌避剤を散布しています」(同)
JR東日本は2023年度から忌避剤の散布を開始し、2025年度には散布するエリアを拡大した。それでもクマ被害が目立つようになっている。しかし、それらを踏まえて「忌避剤を散布する路線や区間をさらに拡大する方針は今のところない」(同)という。
忌避剤の散布は作業員などの安心・安全対策でもあるが、列車を安全に運行するためには欠かせない措置でもある。
11月19日には、JR北海道も2025年度に発生した列車とクマの衝突事故の件数を過去最高の56件と発表。2025年度はヒグマのエサとなるドングリが不作だったことから、エサを求めて人里へと出没しているケースが目立っているという。
列車とクマの事故発生で予想されること
JR東日本や北海道といった鉄道会社がクマについて言及する理由は、列車運行中にクマが線路脇に出没することで運転士や車両といった会社所属の人員や備品だけではなく、乗客にも危険が及ぶからにほかならない。列車内という比較的に安全が確保できる環境でも、クマと衝突して列車が動かなくなってしまうこともある。だからといって車外に避難することもできない。
仮に列車と衝突してクマが動かなくなっても、一時的に気絶していただけというケースもある。その場合、避難中に再び人間を襲う可能性がある。素人が軽々に安全を判断できないため、列車とクマと衝突しすると鉄道会社は地元の猟友会などに連絡する。乗客の安全を第一に考えると、こうした慎重に手順を踏むことは当然のことだが、救助を待つために車内に閉じ込められる。どうしても乗客は負荷を強いられることになる。
市街地だったら救助に駆けつける時間は短くて済むかもしれない。しかし、アーバンベアと呼ばれる市街地に出没するクマが増えたとはいえ、出没地点は山間地であることが圧倒的に多い。狭い車内で長時間にわたって救助を待つことは、想像以上に精神的ストレスになる。