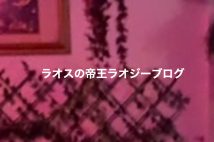『睡蓮』/白石一文・著
【書評】『睡蓮』/白石一文・著/新潮社/1980円
【評者】松尾潔(音楽プロデューサー・作家)
ぼくが40代も終盤になって小説執筆に本気になったのは、白石一文に「小説を書くべきだ」と諭され、心が動いたからだ。あれは人生に幾度もない〈引き返せない瞬間〉だったと、今ならわかる。白石さんの新作には、そんな〈引き返せない瞬間〉をめぐる諸相が、作者ならではの筆致で描き込まれている。
主人公は元新聞社勤務の櫻子、67歳。最愛の兄・貴之の没後17年、兄の元妻である智子(72歳)と1年半ぶりに再会する。幼なじみ同士の結婚、突然の離婚、そして再婚。妹の胸に刺さった「なぜ?」が、終活の時間の中でようやく言葉を得る。
智子が語り出すのは、モネの「睡蓮」に人生を決定づけられたという不思議な告白と、貴之の死の直前、彼が救いを求めた相手のこと。二人の対話が、家族が抱えてきた〈きれいな物語〉を少しずつ剥がし、それぞれにとっては真っ当な、だがいびつな愛の輪郭を露わにしていく。
元新聞記者の櫻子は、事実を確かめるように会話を積み重ねる。だがその理性の下で、エリートだった兄への崇拝にも似た感情が揺れ、読者もまた「身内の英雄」をどう手放すかを問われる。タイトルの睡蓮が示すのは、美しく咲く花、静かな水面、その下に沈む泥の濁りという重層構造か。すなわち、人生。
白石作品らしく、後半生でじわりと効いてくる選択の余波が主題だ。愛を守る器にも個人を縛る枷にもなりうる「結婚」の両義性を、老いと介護、再出発と結びつけて描く筆はいたって冷静で、読み進めるうちに静かな痛みを覚えるかもしれない。
読後に残るのは断罪でも救済でもなく、「私は、この私の人生を(夫から)取り戻さなきゃいけない」という智子の心の叫びだ。静かな圧が、読む者の現在地をそっと照らす。その光はけっして眩しくはない。だが、残された人生を歩み出すための、確かな足がかりになるはずだ。
※週刊ポスト2026年2月6・13日号