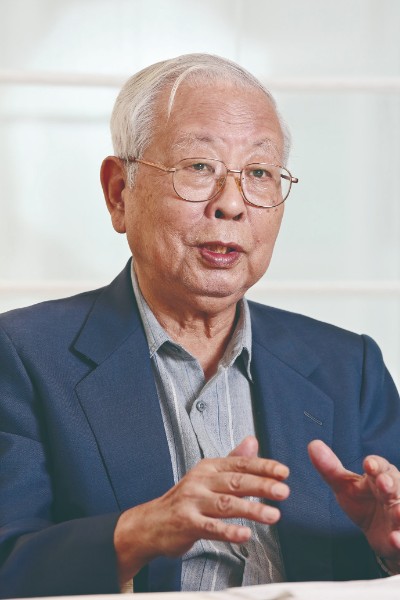現代史家の秦郁彦氏
戦前・戦中の出来事に関して昭和21年に側近へ語った談話をまとめた『昭和天皇独白録』によれば、これについて天皇ご自身は「若気の至りである」と反省されていたようだ。
天皇がこのような行動を取ると、「君側の奸」として、側近たちが非難され、暗殺の対象にされてしまう。それに気づいた昭和天皇は、政治介入と疑われるような言動は自粛していた。
しかし昭和11年の二・二六事件では岡田啓介首相が一時的に行方不明となり、内閣が機能不全に陥ってしまう。やむを得ず、宮中と陸軍のパイプ役である本庄繁侍従武官長に天皇が反乱軍の鎮圧を命じた。ところが、反乱を起こした陸軍の皇道派に近い本庄は動こうとしない。ついに「朕自ら近衛師団を率い、これが鎮定にあたらん」とまで極言するが、それでも本庄は従わなかった。
それでも陸軍に天皇の意向が伝わると、それまで勝ち馬に乗ろうと日和見を決め込んでいた面々が徐々に討伐へ傾く。それまで反乱軍に同調していた石原莞爾(戒厳司令部作戦課長)も、関係者を集めて反乱軍への武力行使を宣言し、「勝てば官軍、負ければ賊軍」としめくくった。
とはいえ、臣下たちがいつも天皇の意向にしたがったわけではない。たとえば対米戦争の方向を決した昭和16年9月6日の御前会議では、明らかに天皇の意向が無視されている。
外交による解決を望んでいた昭和天皇は、その席で「よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐらむ」(*)という明治天皇の御製を読み上げた。
【*「四方の海にある国々は皆同胞と思っているのに なぜ波風が騒ぎ立てるのであろう(なぜ争わなくてはならないのか)」】