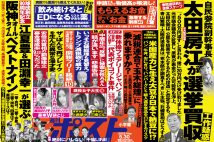「自分らしさを全開にしたらすごく楽になった」(本人提供)
◆“父の顔に泥は塗れない”との一心で
同年4月の初高座では、「人前が苦手で泣いてゲロ吐くほど緊張した」と振り返る貞鏡さん。前座時代は“一龍斎貞山の娘”であることが常にプレッシャーとなった。
「私は講談のことを何も知らずに育ったので、二ツ目を『あにさん、ねえさん』、真打ちを『先生』と呼ぶことも知りませんでした。楽屋でしくじったときに『あらあら、ご両親は何を教えてきたのかしらねぇ』と言われるのが何よりもつらく、心の中で『父ちゃん、母ちゃんゴメン!』とひたすら謝っていました(苦笑)。ぶっちゃけ何回もやめたいと思ったし、原因不明の皮膚病ができたのもしょっちゅう。入門4年目に二ツ目に昇進してからも、同じように暫くはつらい日が続きました」(貞鏡さん)
転機が訪れたのは二ツ目になって2年後だった。たまたま参加したNHKの番組収録後の打ち上げの時、酔っ払ったスタッフから「清純ぶっているけど、それ素じゃないでしょ」「なんで貞鏡さんのままやらないの? 嘘っぽくてつまらない」と唐突に告げられた。
「思ってもみなかった言葉がグサッときました。それまで“貞山の娘だからお利口さんでいないといけない。父の顔に泥は塗れない”との一心で自分を殺し、清楚な学級委員のように振る舞っていたので、『バレたか。だったら全部脱いでやる』と開き直り、自分らしさを全開にしたらすごく楽になった。高座でも、清く正しい良妻賢母を美しい日本語で話すことが多かったけど、素になってからは、毒婦がドスの利いた声で啖呵を切る話を好むようになった。不思議なもので、肩の荷が下りると周りの目が気にならなくなりました。後日、そのスタッフの方に御礼を述べたら、『え? 俺、そんなこと言った?』とちっとも覚えてませんでしたけど(笑)」(貞鏡さん)
吹っ切れてからは、わが道を突っ走り、伝統的な古典講談だけでなく、ピアノを取り入れた「ピアノ講談」や女性落語家らとのユニットなどで幅広く活動する。最近は全国津々浦々の土地にまつわる読み物を披露する会にも力を入れる。