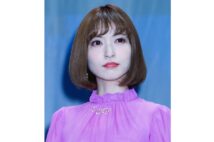吹き抜けが印象的な高輪ゲートウェイ駅(時事通信フォト)
デザインコンペは、あくまでも駅舎そのもののデザインの優劣を競うものだった。しかし、駅舎のデザインコンペを実施する前から、日立市は駅前広場を含む駅前一帯の都市計画を決定していた。
すでに駅前の都市計画は進められつつあり、駅舎のデザインと駅前の都市計画がバラバラに着手されてしまう可能性もあった。ただでさえ、駅前の整備は建築・土木・交通といった、それぞれ分野が独自に動く。これらがうまく連携できなければ統一感のない駅と駅前になってしまう。日立駅にも、同様の懸念が生じていた
「日立駅は日立市にとって顔にあたる施設です。そのため、統一感のない駅前になることは絶対に避けなければなりませんでした。そうした市の意向を妹島さんにも伝えました。妹島さんは意図をきちんと汲み取り、素晴らしい駅舎が誕生しました。日立駅はどこにでもあるような平易な駅舎ではない、魅力のある駅舎になっています」(日立市建築指導課担当者)
駅舎という建築物のみならず、駅と街をトータルで考える。言葉にするのは簡単だが、これは難問でもある。
街の顔になる美しい駅舎は、地域住民の誇りにもなり、末長く愛される存在にもなる。日立駅は素晴らしいでデザインに仕上がったが、構内には海に浮いているような感覚でティータイムを楽しめるカフェも併設されている。このカフェの存在も日立駅の人気に拍車をかけた。
こうした人が交流できるようなコミュニティ機能も駅に求められるようになっている。時代を経るごとに駅に求められる機能は変化し、増えている。それだけに駅舎は建築の知識だけではなく、土木・交通・緑化のほかバリアフリーや防災、省エネといった観点から考えることも重要になっており、くわえて経済学や環境学、公衆衛生学、そして郷土の歴史といった幅広い知識も必要になる。
日本建築学会賞やプリツカー賞の受賞者など、スター建築家が駅舎を手掛けるようになってきているが、そうした事例は実はまだ少ない。
それは、先述したように駅は単に建物の外観だけを考えればいいからではなく、駅通路や駅前広場、また駅から市街地へとつながる道路や街並みなどをトータルにデザインしなければならないからだ。そのため、高輪ゲートウェイ駅の吹き抜けや大きなガラス面など、駅と街がつながっていることが感じられるデザインが近年は意識されている。