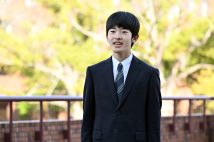電子印鑑の一例(提供シャチハタ、時事通信フォト)
◆課題が山積みのテレワーク導入
では、実際はどのくらいの企業がテレワークを導入したのだろうか。都庁のテレワーク導入率緊急調査結果(2020年5月)によると、都内企業(従業員30人以上)のテレワーク導入率は、3月時点では24.0%だったが、62.7%と2.6倍に上昇した。
ただし全社員というわけではなく、テレワークを実施した社員は12月の15.7%から49.1%まで増えたものの、結局は全体の約5割にとどまっている。テレワークを実施した日も、4月でも、1ヶ月の勤務日数(約20日)のうち約6割の12.2日だった。
導入率を業種別に見ると、事務・営業職が中心の業種(情報通信業、金融・保険業等)は76.2%、現場作業や対人サービスが中心となる業種(小売業、医療・福祉業等)は55%と、業種によって導入のしやすさには差があったが、それでも3月に比べて3.7倍と導入は拡大していたようだ。
筆者が取材したところ、「そもそも自社のデータに外部からアクセスできないから、一日置きに交代で出勤した」「会社はやはり設備が整っているのを痛感した。必要なプリンタやスキャナもないし、家で仕事をしていると腰が痛くなる」などの声も聞く。
前述のような機器・IT関連問題、社外に書類が持ち出せないなどのセキュリティ上の問題、コミュニケーションがスムーズに行かないなどの問題があり、うまくいかないことも多かったようだ。
また、「緊急事態宣言中ですが、ハンコのために出社しました」という自虐的な投稿をSNS内で何度も見かけた。
クラウド会計ソフトのfreee株式会社によるテレワークに関するアンケート調査(2020年4月)によると、「テレワーク中でも出社が必要となる理由」は、「取引先から送られてくる書類の確認・整理作業」が38.3%と最多だった。続いて、「請求書など取引先関係の書類の郵送業務」が22.5%、「契約書の押印作業」が22.2%などと、紙やハンコのために出社した人は少なくなかったようだ。
しかし現在総務省は、文書が改ざんされていないと証明する「タイムスタンプ」の事業者認定の運用開始を当初の2021年度から20年内に早めると発表している。順調に行けば、”ハンコのための出社”は過去のものとなるかもしれない。
◆テレワーク歴・頻度が高まれば改善の可能性
緊急事態宣言が解除されても、テレワークが続く企業は少なくない。テレワークが向いていた人たちにとっては継続の意向が強く、ある調査では7割が継続希望だという。