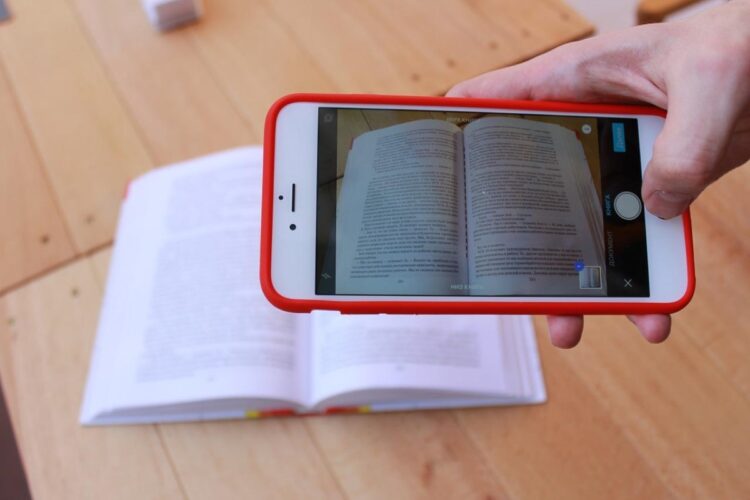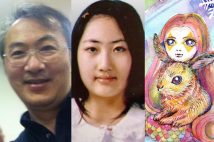ほんの少しくらい、と他人の著作物を引用の範囲を超えて勝手にネット上で公開するのは違法だ(イメージ)
彼ら3人は中国系企業の資本でデジタルマーケティング会社を経営しているとのことだったが、何をしている会社なのかもわからない。もっとも当時のネット系、いわゆる「オタクビジネス」参入企業にはよくある話で、その中には中国系や韓国系もあった。もちろんすべてがそうではなく、中韓であってもしっかりとしたコンテンツビジネスを手掛け、筆者が協力した事業もある。そこはいまや世界的な大企業だ。
「大人気のアニメとか漫画を持ち寄るようなサイトを始めようと思っています」
しかしこの会社は違う。危ない。そもそも「電子漫画の描きおろし」と言うから来たのに、来てみれば「持ち寄るようなサイト」では話が違う。そんなの筆者に言うよりその大手出版社の編集部やライツ(各種ライセンスを扱う部署)に話したほうが早い。
疑念は当たっていた。詳しいことは省くが、のちに見せられた別紙ではあきらかな海賊版サイトの企画だった。
最初からそれが目的だったのかもしれない。先のプロデューサー氏に頼まれての席とはいえ、この時点で1日無駄にしたと思った。
「漫画が欲しいのです。そこであなたにもお願いしたいのです」
最新作や人気の漫画が読めて、みんな喜びます
完全な違法行為なのに大胆である。当時は親告罪だったため(2018年末から非親告罪化)、海外だけでなく日本のアングラなネット企業もまた平気でこれに近いビジネスに手を染めていた。こうした誘惑はこれまでも経験済みだったので、「普通に違法でしょう」とやんわり断る。しつこく誘われたりはしなかった。「あなたにも」ということは他に協力のあてはあるのだろう。あとは誤魔化しのような雑談で終わった。
後日「そんな奴らがいた」と当該出版社の知り合いに話したが、「会社に報告はするけど、多すぎてね」と半ば諦めの声が返ってきた。時代もあるが、その気持ちはわかる。
こうした時代を経て、いまや外国人たちが独占状態で堂々と「漫画の海賊版サイト」を運営している。先に触れた通り2018年末から日本でもTPP絡みで著作権法が非親告罪化したが、現状は「やった者勝ち」で限定的、とくに外国人相手にはお手上げだ。
筆者も出版社時代に海賊版サイトや違法アップロードの対処経験があるが、確かに現実は「削除申請」が関の山だった。勝手に使われて、なぜこちらがお願いしなければならないのか理不尽な話だが、丁重にお願いして削除してもらう。警告より効果があったように思う。実際、削除してくれるサイトはマシなほうで完全無視を決め込むところもあったし、嫌がらせなのかひたすら文字化けだらけの簡体字らしきメールボムを大量に送りつけられたこともあった。
筆者の手掛けたニッチな雑誌や漫画、ドラマCDなども勝手に使われたり、流されたりだったが、2000年代はそれこそ何もできなかった。これは本当に悔しいことであり、いま訴えている出版社やクリエイターの気持ちはよくわかる。自分が作り出したものを好き勝手されるという痛みは人気・不人気、メジャー・マイナーの問題ではない。
中国人はこうも言っていた。
「最新作や人気の漫画が読めて、みんな喜びます」