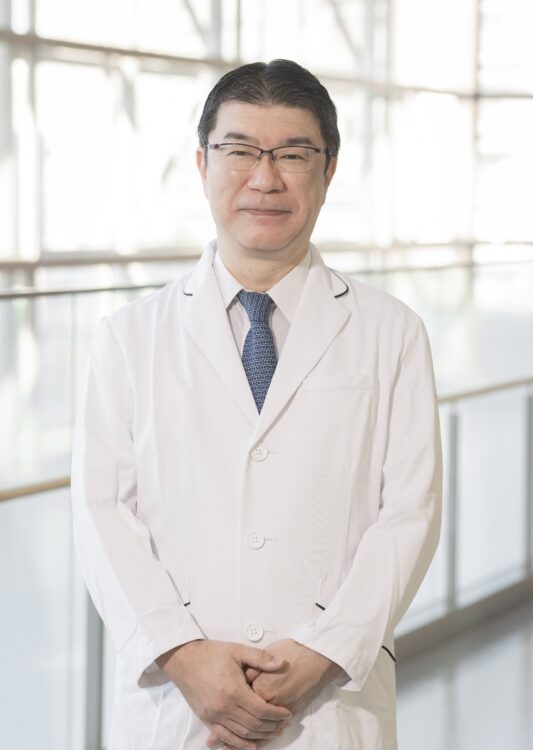大野真司医師
手術数は多すぎてもいけない
では、乳がんと診断されたら、どのような医療機関にかかるべきだろうか。がん研究会有明病院(東京都)で副院長兼乳腺センター長を務め、2023年9月から相良病院(鹿児島県)の院長に転身した大野真司医師はこう話す。
「どこに行けばいいかわからない場合は、一定の基準を満たしている医療機関を受診してください。具体的には『都道府県がん診療連携拠点病院』『日本乳癌学会基幹施設・連携施設』『日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構基幹施設・連携施設』などに認定されているところを選ぶといいでしょう。
また、乳がんの場合、乳腺専門医、乳腺外科専門医、がん薬物療法専門医、臨床遺伝専門医などの資格を持つ医師がいることも重要です。専門資格はいらないという医師もいますが、一定の知識と治療経験がなければ専門医にはなれませんから、やはり資格はあった方がいいと思います」
加えて、がん治療は一般的に手術件数が一定以上ある施設の方が、医師の経験が積み重なるため、治療成績がいいとされている。乳がんの場合も同様で、大野医師は「100例以上が目安になる」と話す。ただ、多ければ多いほどいいというわけでもない。名古屋大学医学部附属病院乳腺・内分泌外科教授の増田慎三医師はこう指摘する。
「一人ひとりの患者さんに真摯に向き合おうと思うと、年間100人が限界です。つまり1人の医師が200も300も手術している病院は、1人の患者さんにかける時間や労力が少ない可能性がある。
私自身もかつて年間150〜180例の執刀を担当したことがありますが、若いからこそできたこと。診断・手術と治療の腕を向上・維持するためにも、年間100例は経験すべきだと思いますが、医師2、3人で200〜300例くらいこなしている施設がちょうどいいのではないでしょうか」
増田慎三医師
電流で焼き固める最新治療
日進月歩の医学の世界において、最新治療を取り入れているかどうかも病院選びにおいて1つの判断基準になる。
がんの治療は、最新の臨床試験で得られたエビデンス(科学的証拠)に基づき、その時点で最も効果的とされる「標準治療」が各学会によって「診療ガイドライン」としてまとめられており、乳がんも「日本乳癌学会診療ガイドライン2022年版」が作成され、同学会のウェブサイトに公開されている。
そのガイドラインに沿った治療方針は、「進行度」(大きさやリンパ節転移があるか)や「組織型」(がんの悪性度が高いかどうか)、「サブタイプ分類」(どの薬物療法が適しているか)などによって細かく異なってくるが、多くの人が「手術」「薬物療法」「放射線療法」のいずれかを受けることになるのは共通している。
かつては、がん細胞を徹底的に取り除くため、乳房だけでなく胸筋まで広範囲に切除する手術や、体に強いダメージを与える大量の抗がん剤治療が行われたこともあった。